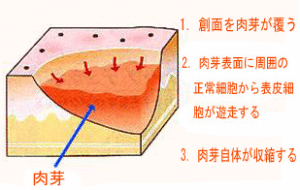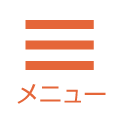ブログ・コラム
Blog2017.10.31(火)
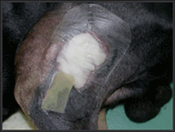
「ドーベルマンの左大腿部にできた拳大の腫瘍(血管周皮腫)を切除し縫合したが、離開してしまった」とのことで紹介されてきた症例。初診時の治療前の写真が無いのが残念であるが、離開創は約10cm四方もあり、深さも3cm近くある大きな陥没創となっていた。創面には血餅や壊死組織が大量に見られたため水道水で洗浄しながら除去した。また同時に周囲の組織にうっ血が見られたが、これは恐らく「足りない皮膚」を無理に寄せて縫合したためテンションがかかり、組織が締め付けられたためと考えられた。したがって無理なテンションがかかっている部位の縫合糸を全て抜糸し、開放創とした。写真は、創面に生理食塩水に浸したガーゼを当て、フィルムドレッシングで被覆したところである。生食ガーゼの交換は1日3回行った。これにより創面の壊死組織の除去と乾燥の防止が可能となる。

治療開始後4日目。創面の肉芽組織の増殖は良好である。傷は大きくなったように見えるが、実は縫合創のテンションが解除され、元のあるべき大きさに戻ったためである。この傷を外科的に閉鎖するためには、ほぼこれと同じ大きさの「皮弁」を使わなければならない。高齢でもあり、飼い主も手術を望まなかったため、このまま被覆材による「閉鎖療法」で上皮化させることとした。
うっ血も消え、壊死組織も無くなったので、ハイドロポリマー・ドレッシングによる被覆を開始し、3-4日に一度交換することにした。

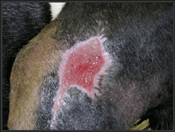

上の写真は左から「10日目」「14日目」「18日目」である。肉芽組織の増殖は極めて良好であり、創面は急速に縮小しているのがお解かりのことと思う。一番右の写真(18日目)では上皮化もかなり進んでおり、創面の面積は4×5cm程度に縮小している。 このころより被覆材をポリウレタンフォーム・ドレッシングに切り替えた。

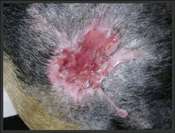
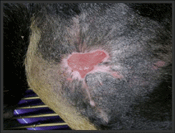
一番左は39日目のものである。かなり上皮化が進み、上皮化していない部分は中心部分の1cm四方のみを残すだけとなった。治癒前半に比べて時間がかかっているように感じられるかもしれないが、これは肉芽組織を形成する「繊維芽細胞」に比較して、上皮細胞は増殖が遅いためである。しかしながら、これだけ大きな陥没創が外科的に手を加えずに40日程度でほぼ治癒しているのは、当初の予想を上回るスピードである。
真ん中の写真は、 41日目のものであるが、このとき残念ながら患者(ドーベルマン)自身が傷をかじってしまい、せっかく上皮化した部分を大幅に破壊してしまった。出来上がったばかりの上皮は非常に薄くデリケートなので、犬が舐めたりかじったりすればひとたまりも無い。再上皮化にはさらに時間がかかることが予想される。右は50日目のものである。この辺りではハイドロコロイド・ドレッシングとポリウレタンフォーム・ドレッシングを状況により使い分けている。

さらに9日後の59日目、ゆっくりではあるが徐々に再上皮化している。

それから約10日後、治療開始時から数えて70日目、完全に上皮化した。
本症例では、筋肉層まで露出する非常に大きな陥没創であったにも関わらず、約2ヶ月程度で完全治癒となった。途中でのアクシデントが無ければ1ヶ月半くらいで上皮化していたものと考えられる。当初の予想では2-3ヶ月かかるものと思っていたが、最初の段階での肉芽の増殖が非常に良好であったのが治癒期間短縮の大きな要因であったように思う。
治癒後の傷は、瘢痕収縮も無く運動の妨げとなるような拘縮もまったく見られない。
本症例の治療全般にわたり、傷の洗浄には生理食塩水ではなく水道水を使用した。また感染徴候は一度も見られなかったため、抗生物質は一切使用していない。
2017.10.31(火)
◆「褥創」とは何か
「褥創」と言う言葉を聞いたことがあるでしょうか?解り易く言えば、「床ずれ」のことです。人間では、寝たきりのご老人など、長期間ベッドに横になったまま自由に体を動かすことが出来なくなった患者さんなどでよく見られます。腰骨や仙骨部、踵など、骨が飛び出した部分がベッドに圧迫されて、筋肉や皮下組織が血行障害を起こして壊死し、皮膚が破れて穴が開いてしまった状態を言います。
褥創は、管理の仕方が悪いとどんどん深くなって、骨が露出してしまうこともあります。また感染を起こして化膿してしまうと、非常に強い悪臭を伴い、菌が全身に回って敗血症と言う状態になり、命に関わることもあります。特に屋外で飼育されている動物の場合は、褥創が出来ているのに気がつかずそのままにしていると、ハエが卵を産みつけて「ハエウジ症」と呼ばれる状態になってしまうこともあります。
褥創が出来る原因はもちろん、病気や老衰のために「立てない」状態になることです。多くの場合は「寝たきり」の状態になって、腰(大転子)や肩、踵などに褥創が出来るのが一般的ですが、後肢麻痺などで前足だけで歩き回っているような場合でも、「本来地面について歩かない部位」を接地して歩いていると、その部分に褥創ができます。また褥創が出来やすくなる要因として、栄養状態が悪く痩せていたり、糖尿病や腎不全などの基礎疾患を持っていたり、便や尿が皮膚にこびりついていたりするような衛生環境の悪い状態などを挙げることが出来ます。小型犬や猫などの小さな動物では、体重が軽いため、あまり褥創は見られません。それに対して、中型犬以上の体重の重い犬では、寝たきりになるとすぐに褥創ができます。特に癌の末期や痴呆により立てない状態になった場合には、栄養状態も悪くなるため、痩せて骨が出っ張ってくるので、体の様々な場所に褥創が出来やすくなります。
当院では「創傷治療」に力を入れており、様々な「治り難い傷」の治療を行っています。そして当然ながら褥創もその中のひとつであると捉えています。しかしながら、「褥創」が出来るような患者と言うのは多くの場合、高齢や慢性疾患の末期などで自宅療養しているケースが多く、また「寝たきり」の20kg、30kgあるような犬を車で運んで通院するのは本人も家族の方も非常に大変なため、「褥創」の治療のために動物病院に通院する、というケースはあまり多くありません(と言うか、殆どありません)。大抵の方は自宅で、自己流で「パッド」をあてたり消毒したり、何か薬を塗ったりしてそれぞれに管理していることが多いようですが、うまく行かずに相談を受けることも時々あります。動物の高齢化に伴い、恐らくかなり多くの方が「褥創」の管理に苦労しているのではないかと思われますが、上記のような理由により、私たち獣医師が「褥創治療」に関わるチャンスと言うのは思いのほか多くはありません。
このような状況をもっとよく知るため、そして誰にも相談できず「褥創治療」に苦労し、悩んでいる方たちのために、少しでも力になれるようにと考え、「褥創の治療」について少し纏めてみることにしました。
以下に詳述するのは、私の今までの経験と「創傷治療」一般から得た知識、および人間の褥創治療を参考にした、現段階で考えられる「最良であろう」と思われる褥創の管理方法です。しかし、実際の管理方法は、褥創の場所や大きさ、深さ、壊死組織や感染の有無、動物の全身状態(全く動けないのか、寝たままでも這いずり回るのか、など)、基礎疾患の有無、動物の性格などにより、個々のケースで変えてゆく必要があります。また、以下に説明する方法が将来的にずっと「最良の方法」であり続ける、とは考えておりません。以下の方法を参考にしていただき、うまく行かない点、問題点などがあれば、掲示板かメールなどで遠慮なくご意見を頂きたいと思っています。なるべく多くのご意見を参考にしながら、より良い管理方法を、皆様と一緒に考えてゆきたいと思っておりますので、ご協力お願いいたします。
2017.10.31(火)
「自宅で傷の治療をしてみたいが、医療用の被覆材は手に入らないし、どうすればよいか教えて欲しい」という相談を受けることが最近増えてきたため、自分で簡単に作れる「開放性ウェットドレッシング」の一例を紹介します。
ここで紹介するドレッシングは、浸出液(漿液)が沢山出るような開放創の治療や、褥創の管理などに利用できます。もちろん「医療用」の材料ではありませんので、ご自宅で自分で治療される場合には「自己責任」で実施されるように、お願いいたします。傷や褥創の治療は、基本的にはお近くの主治医の先生の指示で治療されるのが良いと思いますが、様々な事情によりそれが困難・不可能な場合には、出来る限りご相談に乗りたいと思っています。しかしメールやネット上での「遠隔治療」にはどうしても限界がありますので、治療結果に対しては責任を持つことができない、ということだけは、どうかご了承ください。
以上のことをご理解して頂き、創傷治療や褥創管理に関する知識を充分お持ち頂いた上で、ご自分の判断で使用してください。
「創傷治療」の理解を深めるには、こちらのサイトが大変参考になります。
→ 「新しい創傷治療」
「褥創の管理」の理解を深めるには、こちらのサイトが大変参考になります。
→「褥創のラップ療法・開放性ウェットドレッシング療法」
①まず、台所の三角コーナーなどで使用する「水きり用ポリ袋」を用意します。

中から1枚取り出します。
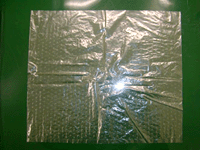
②介護用の紙オムツを用意します。紙オムツはフラットタイプ(長方形の平らなタイプ)がお勧めです。白十字の「サルバLLD」の吸水部分はペーパータイプなので、切ってもポリマーの粉が出ないので便利です。
これを約1/3の長さに切って、先ほどのポリ袋に入れます。
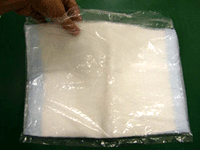
③紙オムツが袋の中でずれないように、紙オムツの裏面とポリ袋を1ヶ所、テープで固定します。
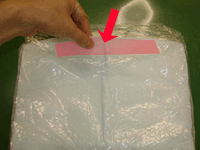
④ポリ袋の口を紙テープで留めて、しっかり蓋をします。
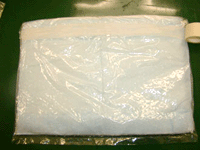
⑤出来上がり。オムツの表側(白い方の面)が、傷(褥創)にあたるようにして、大きく被せます。
ポリ袋で被覆されるので、創面の乾燥を防ぐことができます。染み出てくる浸出液は、ポリ袋の小穴を通ってオムツに吸収されます。厚みがないので、褥創に使用しても「圧迫」になりません。
動物で使用する場合の問題点は、「どうやって固定するか」です。厚手の幅の広い包帯を使用したり、人間用のストッキングや「ストッキネット」を使用しても良いでしょう。
「寝たきり」で、あまり動かない子の場合は、マットやクッションの上に直接これを敷くだけでも構わないかもしれません。
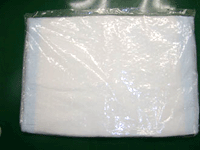
2017.10.31(火)
「ドレッシング材」という言葉は、一般の方にとってはあまり聞きなれない言葉ではないでしょうか?「ドレッシング」と言っても、サラダにかけて食べるものではありません。傷を保護するために巻いたり覆ったりするものを総じて「ドレッシング材」と呼びます。従って、広い意味では昔から使われている「ガーゼ」や「包帯」もドレッシング材の仲間に入ることになります。しかし現在では、ガーゼや包帯の他にも様々なドレッシング材が開発されています。
ドレッシング材には色々な分類のしかたがあります。昔から使われているガーゼや包帯などに対して、新しく開発されたものを「近代ドレッシング」などと呼ぶ場合もあります。「傷を乾いたガーゼで治療するとどうなるか」のところでも説明しましたが、ガーゼや包帯には湿潤環境を保つ働きが無く、傷が乾燥してしまい治癒が遅れてしまいます。新たに開発されたドレッシング材の中には、創傷面の湿潤環境を保つために創面を密閉するものもあり、その性質から「閉鎖性ドレッシング」と呼ばれたりしています(全ての近代ドレッシングが「閉鎖性」と言う訳ではありません)。
ここでは、創傷面の湿潤環境を保ち、苦痛をを与えず傷を早く治すのに非常に役に立つ「近代ドレッシング」の一部を紹介します。
1)フィルムドレッシング
ポリウレタンで作られた、薄い透明なフィルム状のドレッシング材。粘着部分のシールを剥がして皮膚に貼り付けて、傷を密閉する。手術後の縫合創や、アルギン酸、ハイドロジェル(下記参照)を覆うための「二次ドレッシング材」として使用する。写真は腹部の縫合創を被覆するために使用したもの。こうするとカサブタができずに、きれいな縫合創となる。
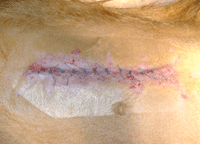
2)ハイドロコロイド・ドレッシング
「カラヤガム」という親水性のコロイドと、薄いポリウレタンフィルムの2層からなっているドレッシング材。親水性コロイドの面に粘着性があり、こちら側が傷と接するようにして使用する。コロイドは浸出液を吸って「ドロドロ」のゲル状に溶けて、創傷面の湿潤環境を維持する。深い傷や浸出液の多い傷ではこの「ドロドロ」が直ぐに漏れ出てきてしまうため、このような傷の治療には向いていない。薄手のもの(写真左)と比較的厚めのもの(写真右)がある。
最近Johnson&Johnsonから発売されている「キズパワーパッド」という製品はこのハイドロコロイド・ドレッシング材である。
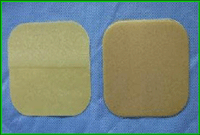
3)ポリウレタンフォーム・ドレッシング
細かい気泡を含んだスポンジ状のポリウレタンで出来たドレッシング材で、表面はやはり薄いフィルムでコーティングされている。厚みがあり吸水性に優れているため、比較的浸出液の多い傷を覆うのに使用できる。これ自体には粘着性が無いので、粘着包帯などを利用して固定する必要がある。細く切ってドレインとしても使用できる。
写真は半分に切って裏面と表面を同時に見えるようにしたところ。下側の白い方を傷面に当てて使用する。
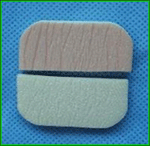
4)ハイドロジェル・ドレッシング
無色透明のジェル状のドレッシング材。一見「塗り薬」や軟膏剤のように見えるが、これもれっきとしたドレッシング材である。乾燥気味の傷や壊死組織の残った傷に使用する。親水性のジェルの中に浸出液を保持して、浸出液に含まれる自己融解酵素を活かしながら壊死組織を少しずつ溶かすような場合に有効である。単独では使用できないので、フィルムドレッシングやポリウレタンフォーム・ドレッシングなどと合わせて使用する。

5)アルギン酸ドレッシング
昆布の抽出液から作られた綿状のドレッシング材。浸出液を吸収してジェル状に溶ける。もともとはその吸水性を活かして浸出液の多い創傷に使用される目的で作られたが、現在ではもっと吸水性の優れたドレッシング材が入手できるため、あまりこの目的での利用価値は無い。しかし、止血作用に非常に優れているため、出血を伴う新鮮外傷に対する初期治療に使用するドレッシング材として非常に有用である。単独で使用すると乾燥して固まり、「カサブタ」のように傷にくっついてしまうので、必ずフィルムやハイドロコロイドなどのドレッシング材と合わせて使用する。
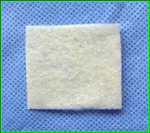
6)ハイドロポリマー・ドレッシング
親水性のポリマーとそれを覆う粘着性のカバー素材の2層からなっている。ハイドロポリマーは吸水性に優れており、比較的大量の浸出液を伴う傷に使用できる。浸出液を吸収すると、ポリマーは傷の形に合わせて膨張し、創傷面にフィットする。従って、このドレッシング材は浸出液が多く、深い傷に使用するのが便利である。写真はハイドロポリマー部分に水道水を含ませて膨張させた様子。
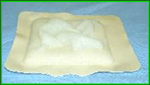
7)食品包装用ラップ
サランラップ、クレラップなどの食品用のラップである。当然ながらこれらの製品は「医療用」ではない。しかしながら、ラップは非常に優れたドレッシング材として傷の治療には重宝している。基本的にはフィルムドレッシングと同じような使用法をすることが多いが、粘着性が無いために「完全な密閉状態」にはならない。つまり「半閉鎖」状態となるので、浸出液の多い傷にも使用できる(もちろんラップの上から吸水性のパッドなどを当てる必要がある)。ハイドロジェルなどと合わせて使うのにも便利である。また非常に薄いために創傷面を圧迫することが無く、褥創(床ずれ)の治療にも有効である。
2017.10.31(火)
▽はじめに
全ての傷はひとつとして「同じ」ものはありません。一見同じように見える傷を同じように治療した場合でも、治癒までの期間に大きな差が出る事も珍しくありません。傷の大きさや深さなどの条件のほかに、傷のある場所や傷を持つ動物の動物種、年齢、栄養状態、遺伝的性質などの身体的条件も、治癒に大きく関わってくるからだと思われます。従って、全ての傷の治療に通用する「唯一つの治療法」というのは存在しません。傷の状態を見ながら、その度ごとに適切な治療法を選択し、経過を観察しながら必要に応じて治療法を変えてゆくことも大切です。
しかしながら、多くの傷の治療に関して共通した「注意点」と言うものは存在します。ここでは、幾つかの傷の状態に応じて「これだけはすべき」というポイントを簡単に説明します。
▽「感染創」か「非感染創」かを区別する
「創傷感染の定義」のところで説明したとおり、「腫脹」「疼痛」「発赤」「熱感」の「炎症4徴候」が見られるか、明らかに膿が溜まっているような場合には「感染創」と判断されます。ただし、「膿」と「浸出液」は全く違うものですから間違えないように注意する必要があります。
「感染」があると判断された場合には、抗生物質の全身投与を行います。また感染徴候が無くなるまでは、閉鎖性ドレッシング材による密封はすべきではありません。
▽「異物・壊死組織・膿」は完全に取り除く
傷の中に入り込んだ汚染物質や壊死した組織はできる限り早めに取り除きます。火傷などの傷では、最初の段階では完全に壊死組織を取り除く事が出来ないこともあるので(数日かけて徐々に損傷組織の壊死が進行してゆくため)、このような場合には治療のたびに少しずつ壊死組織を取り除いてゆきます。異物や壊死組織は「細菌」の増殖の場になりますから、これらが残っている状態では傷を密閉すべきではありません。
新鮮外傷では、傷の中に土や植物片や毛などの異物が入り込んでいる事がよくあります。これら異物をしっかり洗い流す事が大切です。傷の洗浄は生理食塩水でも構いませんが、大量の流水が必要な場合は水道水で充分です。

猫の背中に出来た膿瘍
大量の膿と壊死組織が見られる
▽ドレナージをする
「ドレナージ」とは過剰な体液を排出させる事を言います。「浸出液」は傷の治癒に必要である、と書きましたが、中には浸出液が過剰に分泌されすぎて、傷の管理がうまく行かない場合もあります。このような場合には、過剰な浸出液を傷の外に出すように、チューブやドレイン用ガーゼなどを使って「排液」をすることが大切です。ポケット状の傷の中に膿が溜まっている「膿瘍」などの場合には、膿を排出させた後、傷口が直ぐにふさがってしまわないように、ドレインを入れておくことが必要になります。
▽適切なドレッシング材を選択する
傷を保護したり、湿潤環境を守るために傷を覆うものを「ドレッシング材」と言います。ドレッシング材には様々なものがありますが、傷の状態に応じて適切なものを選択し、適切な期間で交換する事が重要です。治癒の経過が良くない場合には、治療法を臨機応変に変えてゆくことも大切です。ドレッシングには傷を完全に密封するもの、ある程度通気性を残した「半閉鎖性」のもの、ジェル状のもの、ガーゼのように閉鎖性の全く無いものなどがあります。上記にもあるように、感染の治まっていない傷、壊死組織や異物が完全に取り除かれていない傷は「密封タイプのドレッシング材」を使用すべきではありません。
▽上皮化
ドレッシング材の選択と交換の間隔が適切なら、傷は徐々に修復して行きます。深い傷の場合にはまず、線維が細胞からなる「肉芽組織」が増殖して来ます。そして肉芽組織の上に表皮細胞が移動して、傷が上皮化します。もちろんこの時、ドレッシング材を使ってゆっくり上皮化させるのではなく、外科的な方法により手術で傷を閉じるのも選択肢の一つです。
治癒したばかりの傷は上皮がまだ薄く、不安定なため、動物が舐めたり引っ掻いたりしないように物理的な保護をする必要があります。また紫外線により刺激を受け易いため、人の場合などは特に、上皮化してから半年くらいは日焼け止めクリームを塗って皮膚を保護する必要があります。動物の場合には「日焼け止めクリーム」を塗る必要性を感じた事はありませんが、治癒後数ヶ月間は長時間紫外線を浴びるような状況を避けた方が良いでしょう。