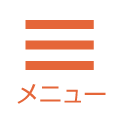ブログ・コラム
Blog2017.06.02(金)
梅雨から夏にかけては気温も湿度も上昇し、「蒸し蒸し、ジメジメ」として来ます。この時期は私達人間にとっても過ごし難い季節ですが、「全身毛に覆われ」「汗をかくことが出来ない」犬や猫たちにとっては、特に過ごし難い季節となります。
梅雨の季節に罹りやすい病気や、暑い時期に注意すべき点などを以下に幾つか挙げておきましたので、これらのことに気を付けて暑い季節を「健康」に元気良く乗り切ってください。
● フィラリア・ノミなど寄生虫の予防
気温が暖かくなってくると活動を始めるのは蝶やバッタなどの昆虫ばかりではありません。ノミやマダニなどの、人や動物にとってあまり有難くない「虫」;即ち寄生虫などの「虫」もまた、活発に動き始めます。フィラリア(犬糸状虫)を媒介する「蚊」もまた同様に、暖かくなると吸血を始めます。ノミやマダニなどの「外部寄生虫」は、痒みや皮膚炎の原因になるだけではなく、ウイルス病やリケッチア、原虫など病原性微生物を媒介することでも知られています。これらの感染症の中には人にも感染する可能性のある「人畜共通感染症」も含まれていますので、確実に予防することが大切です。
● 熱中症
環境中の湿度や温度が上昇することで最も気をつけなければならないのは、この「熱中症」の発生です。真夏に庭や日陰の無い広場などの屋外に犬を長時間放置したり、激しい運動をさせたりすると、体温が異常に上昇して「熱中症」になることがあります。また風通しの悪い室内で留守番をさせたり、外出時に車の中で待たせたりすることで、熱中症を引き起こすこともあります。高齢の動物、肥満傾向のある動物、短頭種(ブルドッグ・パグ・シーズー etc…)、超大型犬、皮毛の密な犬種(北方原産の犬;S.ハスキー・サモエド・キースホンド etc…)などでは、熱中症を起こす危険性が高いと考えられます。また黒い毛色を持つ犬は、野外で日射病にかかる危険性が上昇します。犬以外の動物では、ウサギやモルモットなどが「暑さ」に非常に弱いことが知られています。
熱中症を防ぐためには、動物を「暑く、湿度の高い」環境に置かない、と言う事が大切です。室内で留守番をさせるときには風通しを良くして室内の温度を調節すること、場合によっては(昼の最も暑い時間帯には)軽くエアコンをかけてあげることも大切です。また新鮮で清潔な水をいつでも摂取できるようにして、脱水を予防することも非常に重要です。
● 皮膚病
ノミやダニの発生に伴って、暖かい時期には「皮膚のトラブル」が多発します。もちろんアトピー性皮膚炎などのアレルギー性疾患は秋や冬に悪化する場合もありますし、全ての皮膚病が春・夏に発生する訳ではありません。しかし、何らかの原因で発生した皮膚炎が細菌やカビなどの二次的な増殖により悪化したり、ノミアレルギーを併発したりして重症化してしまうことは、これからの時期には良く見られます。また夏場にはキャンプなどで野山に行く機会も増えることと思われますが、山道や草むらを歩き回って体中にマダニが寄生してしまう、などという事もよくありますし、川で泳いだ後そのままにしておいたために皮膚炎を起こして、お腹や腋の下の皮膚が真っ赤になってしまった、というケースもあります。川や沼地などで犬を泳がせた後は、水道水で汚れた水をきれいに洗い流した後、被毛を乾かしてあげてください。
● 食餌について
最近は自分達の食べるものだけでなく、犬や猫などの動物達に与える食餌についてもこだわりを持つ人が増えてきました。これに合わせてペットフードも「無添加」を謳ったものが増えてきました。保存料などが無添加の食餌を与えることは決して悪いことではありません。しかし「保存料が含まれていない」と言う事は、それだけ「腐りやすい」ということでもあります。梅雨時や夏は特に、フードにカビが生えたり劣化したりし易いので、充分注意する必要があります。一度封を切ったドライフードは毎回しっかり蓋をして涼しい場所に保管し、出来るだけ短い期間(できれば2週間以内くらい)で食べ切るようにしてください。缶詰フードの場合は、一度開けてしまうと冷蔵庫に保管しても数日でカビが生えてしまう可能性があります。小型犬などの場合で、1缶を1~2日で食べきれないような場合には、少々面倒ですが1回分ずつ小分けにして冷凍し、毎回必要分だけ解凍して与えるという方法もあります。「傷んだ食餌」を与えることは、「保存料」を口にすることの何十倍も体に悪い、と言う事を忘れないでください。
● 中毒など
毒物や薬物による中毒は、梅雨時や夏に限らず1年中いつでも起る可能性がありますが、特にこれからの時期に注意すべきものには次のようなものがあります。
・カビが生えたり傷んだフード(前述の通り)を与える
・殺虫剤、除草剤、殺ナメクジ剤などの薬剤の誤食
・蜂、虻、ムカデなどの「害虫」に刺される
・カエルやトカゲ、ミミズなどを食べてお腹を壊したり寄生虫に感染したりする
・沼地の「藻」や屋外の植物、その球根など(毒を含んだものがある)
特に夏場は動物達(特に犬)を屋外に連れ出したり、キャンプ、旅行などで外出させる機会も増えます。思わぬところで事故に会ったり、迷子になったりすることもありますので、充分に注意してこれからの「楽しい季節」を無事に過ごしてください。
2007.01.22(月)
以前「中毒…」のところでも触れたことのある「キシリトールの毒性」の話ですが、アメリカの獣医専門雑誌「Veterinary Medicine」の2006年12月号に「犬に対するキシリトールの影響に関する新情報」が掲載されましたので、重要な点だけを抜粋して紹介したいと思います。
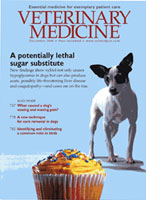
「キシリトール」について
・ キシリトールはヨーロッパ(特にフィンランド、ノルウェイ、ロシア)および日本で一般的な甘味料であり、アメリカでもこの数年でその使用が急激に増加している。
・ キシリトールの摂取は、人では比較的安全性が高いと考えられるが、犬では、摂取により時に命に関わるような重篤な症状を引き起こすことがある。
・ キシリトールの投与が、犬で低血糖を引き起こすことは約40年前から知られていた。しかし最近の研究で、キシリトールの摂取が急性の肝壊死を引き起こすことが判った。
「キシリトールの歴史など」
・ キシリトールは1891年に、ドイツの化学者であるEmil Fisherにより発見された。
・ キシリトールは、イチゴ類やレタス、きのこ類など普通の食物にも含まれている。
・ キシリトールはサッカロース(ショ糖)と同じくらい甘みがあり、カロリーは約2/3である。
・ 人ではインスリンの分泌を殆ど刺激しないため、低炭水化物食を要する人達や、食品中のグリセミック・インデックスが気になる人達のための代用品として優れていると考えられている。
・ キシリトールは特定の細菌の増殖を防ぐことが知られており、子供の細菌性内耳炎の予防に使用されている。また、口腔内の細菌が酸を作り出して歯の表面にダメージを与えるのを抑制することで、虫歯予防の目的でも使用される。このため、無糖ガムや歯磨き粉、その他の口腔ケア製品に多く含まれるようになってきた。
「キシリトールの代謝」
・経口投与されたキシリトールの吸収性は、動物種によって大きく異なる。ヒトとラットでは、ゆっくりと吸収される(だからこそ糖アルコールの過剰摂取により浸透圧性下痢のリスクが高くなる)。ヒトでは口から摂取したキシリトールの49~95%が吸収される。
・ 一方、犬では口から摂取したキシリトールは、急速に、ほぼ完全に吸収される。血漿中の濃度のピークは摂取後約30分である。
「キシリトールの毒性と症状」
・ 多くの動物種において、キシリトールの経口摂取における安全域は広い。マウスにおける経口摂取でのLD50は20g/kg以上である。
・ ヒトでは、キシリトールを1日あたり130g以上摂取すると下痢を起こすと言われているが、それ以外の異常は見られない。しかし、これは犬では全く異なる。
●最初に見つかった副作用
・ 1960年代の実験。犬にキシリトールを静脈投与した場合に、同量のグルコースを投与した場合よりも多くのインスリン分泌を引き起こし、同時に血糖値の低下をも引き起こすことが判った。
・ ある研究では、犬に体重1kgあたり1gのキシリトールを経口投与した場合の血中インスリン濃度のピークは、同量のグルコースを投与したときの約6倍であった。
・ グルコースの投与後は血糖値が上昇するのに対し、キシリトールの投与後は急速に血糖値が低下し、約1時間で50mg/dl以下にまで低下した。
・ APCCは、犬で体重1kgあたり0.1g以上のキシリトールを摂取した場合には低血糖を生じる危険性がある、としている。
・ キシリトール摂取後に通常最初に見られる症状は「嘔吐」である。低血糖は通常30~60分以内に見られるが、キシリトール・ガムを摂取した症例では低血糖の症状発現までの時間が12時間まで延長したものもある(ASPCA APCC Database 2003-2006)。症状は次第に嗜眠、運動失調、虚脱、痙攣発作へと進行する。
・ キシリトールの血糖値に対する影響は動物種によって異なる。ヒト、ラット、馬およびアカゲザルでは、キシリトールを静脈投与しても血中インスリンは殆ど~全く上昇せず、血糖値にも影響がない。これに対して、牛、山羊、ウサギ、ヒヒではキシリトールの静脈投与により多量のインスリンが分泌される。猫、フェレットではよく解っていない。
●「新たに判明した副作用」

・ 最近、ASPCA APCCはキシリトール摂取後12~24時間以内に肝酵素の活性が上昇した犬の事例を幾つか報告した。これらの犬の中には、キシリトール摂取の後、急性肝不全を引き起こしたものもいた。
・ 「警告文;犬にこれらのお菓子を与えないで!」参照;これら8頭のうち6頭では、肝不全の発症前に低血糖が見られなかった。しかし、嗜眠や嘔吐は9~72時間以内に見られている。
・ これらの犬ではまた凝固不全による血液凝固時間の延長、点状出血、斑状出血、消化管内出血が見られた。
・ 血液化学検査ではALT値の上昇、軽度~中程度の高ビリルビン血症、凝固時間の重度な延長などが見られた。また軽度~中程度の血小板減少症やALP値の軽度の上昇、中程度の低血糖が見られた。
・ また、軽度~中程度の高リン血症が見られた。「高リン血症」は予後不良の指標である。
・ 8頭のうち5頭で安楽死、もしくは死亡が認められた。うち3頭で病理解剖が行われた;2頭で重篤な肝壊死が認められた。
・ 現時点では、犬で肝不全を引き起こすキシリトールの容量は、低く見積もっても0.5g/kgとされている(ASPCA APCCDatabase: Published data,2003-2006)。しかし現時点で、この反応が容量依存性のものなのか、特異体質によるものかと言うことは、はっきりしていない。
「キシリトール以外の甘味料について」
・ ソルビトールやマンニトールなどの糖アルコールは、犬に対して血糖値やインスリンの分泌に殆ど(あるいは全く)影響を与えないが、過剰摂取により浸透圧性の下痢を起こす可能性はある。
・ ショ糖やアスパルテーム、スクラロースなどの人口甘味料は一般的に安全であり、もしも大量に摂取したとしても特に疾患を引き起こすことはない、と言われている。
「治療」
・ (省略)
2006.11.30(木)
読売新聞 <http://www.yomiuri.co.jp/national/news/20061128i303.htm?from=main3>
《以下引用》
「細胞を活性化させ、心に安らぎをもたらす」「たばこや排ガスを浄化し、空気をきれいに保つ」――。こんな「マイナスイオン」効果をうたったインターネット広告に、科学的根拠がないものが含まれているとして、東京都は7業者に対し、景品表示法を守るよう指導した。
マイナスイオン商品は数年前から、健康志向に乗って市場を拡大。都は表示に問題がありそうな布団やネックレス、空気清浄器など8商品を選び、業者に資料の提出を求めた。
業者側は「材料のトルマリンからマイナスイオンが発生する」などと説明したが、都で分析したところ、商品の仕組みと合致しない実験データを示していたり、ネット上で見つけた数値を根拠なく引用したりしていて、広告内容には裏付けのないことが判明。都は27日に文書で指導した。
こうした商品の中には数十万円もするものもあり、都消費生活総合センターなどには昨年度までの5年間で計400件の相談があった。都は「科学的な説明に見えても、うのみにしないで」と呼びかけている。
(2006年11月28日11時10分 読売新聞)
《コメント》
「いまさら・・・。」という感がないでもありませんが、残念なことに、いまだに「マイナスイオン」を売りにしている商品が巷に溢れているのが事実です。「ニセ科学シンポジウム」のところでも書きましたが、「水」という物質を専門的に研究している物理学者でさえ、「マイナスイオンとは何か」と言うことについて、「まだきちんと定義されていない」と言っています。「マイナスイオンとは何か?」ということが、まだ判っていないのです。マイナスイオン関連製品の売り文句の中には、「陰イオン」と混同しているような記述もたくさん見られます。「負に帯電した水滴がたくさんある」=マイナスイオンが豊富、という訳の解らない記述もよくあります。滝のそばなど、細かい水滴=霧の多い場所が「カラダに良い」とすれば、それは湿度のためであって「マイナスイオン」を持ち出す必要はありません。空気中のゴミなども、水滴により地面に落ちるため、空気が綺麗になるかもしれませんが、これも「マイナスイオン」とは無関係です。滝や噴水、加湿器によっては、セラチア菌やレジオネラ菌などで汚染された水が霧状に漂っているような場合には、むしろ危険性が高まることもあります。
「マイナスイオン」の定義が科学的にはっきりしない以上、これが「カラダに良い」とか「健康に良い」などという、信憑性のある報告というのは「無い」ということになりますが、これを差し引いて考えても、「体験談」の域を出るものは見当たりません。
因みに、以前にここでも紹介した「誇大広告を見破るための9か条(国立健康・栄養研究所)にもありますが、「体験談」ばかり載っているような健康食品の類は、それだけで「怪しい」と思った方が安全です。
これに良く似た「水」モノで、最近はやりの水に「活性水素水」と呼ばれているものがあります。「活性水素水」に関しては「こちら」をご覧下さい。
「アルカリイオン水」とか 「活性水素水」とか、 とかく日本では様々な怪しげな「水商売」が成り立っています。水の結晶のことを書いた「疑似科学」の本が話題になったこともありますが、かなり大きな社会問題として捉えるべき「大問題」ですが、何故かいまだに学校などで子供たちに配られているそうです・・・子供たちの未来がとても心配です。
2006.11.16(木)
時事通信社 2006/11/16-21:48
<以下引用>
男性が狂犬病で重体=フィリピンでかまれ感染-国内の発症は70年以来・厚労省
厚生労働省は16日、京都市在住の60代の男性がフィリピンで犬にかまれ、狂犬病を発症したと発表した。男性は重体。国内で人が狂犬病を発症したのは、1970年にネパールで感染した日本人男性が帰国後に発症して以来。
厚労省は同日、都道府県や旅行業界団体に対し、狂犬病の流行地域への渡航者に注意を呼び掛けるとともに、万が一動物にかまれた場合はすぐにワクチンを接種するよう通知した。
また、臓器移植などの例外を除き、人から人への感染をすることはなく、同省は「男性から感染が拡大する恐れはない」(結核感染症課)としている。
<コメント>
日本に住んでいると、狂犬病など過去の病気だ、と考えてしまいがちです。しかし世界では、狂犬病はいまだに非常にありふれた感染症です。狂犬病の清浄地域(非発生地域)とされているのは、日本の他にはイングランドやニュージーランド、シンガポール、ハワイなど、世界でもごく限られた11地域だけです。
海外に行ったら、絶対に野犬には触ってはいけません。犬だけではなく、野生動物からも狂犬病は感染しますので、自分の命が惜しい人は、無闇に動物に触らないようにしましょう。もしも万が一動物に咬まれたら、狂犬病に感染した可能性が高いと判断してすぐに病院で見てもらうことをお勧めします。
2005.12.23(金)
クリスマス、お正月と楽しいイベントが続く時期です。この時期は人間の方も食べ過ぎ・飲み過ぎで体調を崩すことがありますが、動物達も決して例外ではありません。浮かれてしまったり気が緩んでしまったりするせいか、ついつい普段は与えないような「ご馳走」をたくさん与えてしまうことがよくあります。クリスマスケーキを「ほんの一口」と言いつつ二口、三口と与えてしまったり、お節料理のおすそ分けをしてしまったり…。もちろん大事に至らないケースもありますが、時にはお腹を壊して下痢や嘔吐・食欲不振などを引き起こしてしまう場合もあります。そんなときに限って病院がお正月休み…などと言うことにならないように、あまりいつもと変わったものを与えるのは控えるようにしてください。
「前編」では、私たち人間が「安全」だと思って日常的に摂取している「食べ物」や「飲み物」が、動物では時として危険なことがある、と言うことを紹介しましたが、今回もその続きです。
人間にとっては安全な食物でありながら、犬や猫などの動物に与えてはならないものの代表としては、「タマネギ」が有名です。タマネギはAllium属(ネギ属)に含まれますが、その他にもガーリック、長ネギ、ラッキョウ、韮(ニラ)、チャイブ(西洋浅葱)などがAllium属に含まれます。アメリカの獣医学専門誌に掲載されたある報告(.pdf)によると、タマネギだけではなく全てのAllium属の植物が、犬や猫たちにとって同様に危険である、とされています。タマネギその他のAllium属には数種類の「有機チオ硫酸化合物」と言う酸化物質が含まれており、これを摂取することによって赤血球の細胞膜が損傷を受け、溶血性貧血を引き起こします。重度の貧血では急性腎不全などを併発して死亡することもあるので充分注意する必要があります。この物質は加熱調理しても変化しないため、すき焼きやカレーライスなど過熱したものでも中毒を起こします。またよくある勘違いとして、「タマネギだけ除ければ大丈夫だろう」と考えて、一緒に調理した肉や他の野菜などを与えてしまい、中毒になることもあります。同じ皿で調理されたものは全て、与えるべきではありません。
アボカドが兎やげっ歯類、鳥類に対して毒性が高いと言うのは比較的知られているのではないかと思いますが、同様に犬や猫、フェレットなどに対しても毒性を示すことがある、と言う報告があります。アメリカのASPCAAnimal Poison Control Center(動物の中毒管理センター)によれば、アボカドの果実、種、葉などにはペルジン(persin)と呼ばれる中毒物質が含まれており、人に対しては毒性を示すことは無いようですが、犬や猫がこれを摂取することで嘔吐や下痢などの消化器症状を引き起こす可能性がある、と言うことです。鳥やげっ歯類ではさらに感受性が高く、呼吸困難や全身性のうっ血を引き起こして死亡してしまうこともあります。従って、人以外の動物にアボカドを与えるのはやめたほうが良いでしょう。
キシリトールはキシリットともいわれ、俗に「ショ糖やグルコースと比べて虫歯になりにくい」、「低カロリーで血糖値上昇抑制効果を持つ」などといわれている甘味料の一種です。ヒトでの有効性については、「虫歯の原因になりにくい」、「歯を丈夫で健康にする食品」として、キシリトールを関与成分とした特定保健用食品が許可されています。一般に「健康によい」と言うイメージを持つキシリトールですが、ASPCA Animal Poison Control Centerの報告によれば、犬が誤って比較的大量に摂取した場合には、急激な低血糖を起こして意識レベルの低下や痙攣などの神経症状を引き起こし、重度な場合には命に関わる可能性もある、とのことで、キシリトールを含んだガムやキャンディーなどを犬が届かないところに保管するように注意を喚起しています。実際にはキシリトールを含んだ犬用のガムなども売られていますが、必要以上に大量に与えるのは「安全」とは言えない可能性もあります。因みにヒトの場合でも、キシリトールを一度に30~40g摂取すると、下痢などの消化器症状や腹痛などを起こすことが知られています。
一般食品ではありませんが、ビタミン剤やサプリメントなども注意が必要です。これらはどこの家庭でもよく見かけるものですし、「健康によいだろう」と考えて、犬や猫などの動物に日常的に与えているケースも多いのではないかと思われます。ビタミンB群やビタミンCなどの「水溶性ビタミン」は過剰に摂取しても尿から排泄されてしまうため、それ程気にする必要はありません(但しビタミンCの過剰症では膀胱のシュウ酸結石が見られることがあります)。しかしビタミンA、D、Kなどの「脂溶性ビタミン」は体内に蓄積してしまうため、多量に摂取すると過剰症を引き起こして様々な障害をもたらす可能性があります。特にDを含むビタミン剤とカルシウム剤を同時に大量に摂取した場合、重度の高カルシウム血症を引き起こして命に関わるケースもあります。実際には、バランスの取れた適正なフードをきちんと与えていれば、一般的にビタミンやサプリメントを添加する必要は基本的にはないはずです。病気の治療のためにある種のビタミン剤などを服用している場合には、不用意にサプリメントを与えると危険な場合もありますので、内容成分をよく確認し、同時に与えても大丈夫かどうか、掛かりつけの動物病院でよく相談されることをお勧めします。
(→ 関連記事;診療日記)