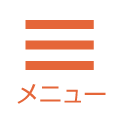ブログ・コラム
Blog2004.10.23(土)
犬や猫、その他の動物達と共に生活することは、安らぎや楽しみなど、私達にかけがえのない時間や経験を与えてくれます。このような素晴らしい経験をした人の多くは、もはや「ペットのいない生活」など考えられないようになるのではないでしょうか?
しかし一方では、「動物を飼う」ということは、重大な責任を伴う「一大事業」でもあるのです。生活環境が変わったから、面倒になったから、と言って途中で放り出すことは出来ません。長期の旅行に行けなくなったり、住む場所が限定されることもあります。病気や怪我をすることだってあるでしょう。実際にペットを飼ってしまってから「さて困った」ということにならないように、今回は「ペットを飼う前の注意」を中心にお話を進めて行きましょう。
【ペットを飼う前に・・・】
ペットと暮らす生活をより快適なものにするためには、実際にペットを飼う前に、様々な準備をする必要があります。多くの場合はまず、どのような動物をペットとして迎え入れたいのか、ということから考えるのではないでしょうか?犬を飼いたい、猫を飼いたい、あるいは小鳥を飼いたいという人もいるでしょう。しかし、「飼いたい」という希望と、実際に「飼うことができる」かどうかということは、別の問題です。「ペット不可」のマンションで動物を飼ってしまったために、結局その子を途中で手放さなければならなくなったり、あるいは部屋を明渡さなければならなくなったりすることもあります。このようなことにならないように、現在の自分の生活環境と、そこでペットを飼育することができるかどうかという現実をよく考えてから、実際に飼う準備を始めなければなりません。
ここで最も注意すべきことは、本来「ペット」に適していない、野生動物などの「珍しい動物」を興味本位で飼うことは、絶対に避ける、ということです。大型の爬虫類や珍しい両生類などを飼育するためには、専門的な知識や特殊な設備が必要となることがあり、一般の方にはあまりお勧めできるペットとは言えません。アライグマやキツネ、リス、サルなどは野生動物なので、ペットとして一般の家庭で飼育すべき動物ではありません。これらの動物は、人に慣れずに逃げ出して野生化し環境問題を引き起こしたり、人に感染する病気を持っている危険性もあり、動物園などの専門的な施設以外での飼育はすべきではありません。人畜共通感染症の問題からプレーリードッグなどの野生リスやペット用のサルが輸入禁止になったのは、まだ記憶に新しいのではないでしょうか。
気を付けるべきは、野生動物ばかりではありません。例えば犬を飼うときでも、どんな品種の犬を選ぶかによって、性格や必要となる生活環境に大きな差が生じてきます。例えば、ワンルームマンションの室内でシェパードなどの活動的な大型犬を飼うことには無理があります。密集した住宅地で、ビーグルなどのよく吠える犬種を飼ってしまうとトラブルのもとになるかもしれません。また今まで殆ど犬を飼った経験のない人や、しつけに関する知識のあまりない人にとっては、日本犬や気性の激しいテリア系などの犬種は、飼育が難しい場合もあります。ついつい犬を甘やかしてしまい、厳しくしつけることが苦手なタイプなのか、リーダーシップを持って犬との主従関係・信頼関係をしっかり築くことができるタイプなのか、自分自身の性格によって、適している犬種とそうでない犬種があります。自分では犬好きだと思っていても、実は猫との相性の方が良い、ということもあるかもしれません。
それから、非常に現実的な話になりますが、自分自身の経済状態も、ペットを飼う上で事前に考慮すべき項目のひとつです。たとえ保護したり譲り受けたりしたような場合でも、その動物を責任を持ってきちんと飼って行くということは、思ったよりお金のかかることです。ワクチンやその他の予防には毎年決まった金額の出費がかかりますし、不妊手術にもそれなりの金額が必要になります。特に大型犬を飼うような場合は、食費も薬代も、猫や小型犬の場合の何倍ものお金が必要になりますし、病気をして手術や入院をしたときには更に・・・。お金の話ばかりすると空しくなってしまうかも知れませんが、ご自分の経済状態に見合った動物を選ぶことは、自分自身とペットとなる動物、両者の幸せにとってとても重要なことなのです。
悲しいことに、ペットの人気にも流行り、廃りがあります。しかし、「テレビのCMで流行っているから」とか、「好きな芸能人が飼っているから」というような安易な考えでペットを飼うことは、絶対にお勧めできません。またプレゼントとして子犬や子猫を他人に贈ることも、是非とも避けて頂きたいことのひとつです。
実際に飼ってしまってから、「こんなはずじゃなかった」と後悔することがないようにするためには、自分自身の生活環境や性格にあった動物を、パートナーとして選ぶことが非常に大切です。
【実際にペットを飼う際の注意】
ペットの入手先としては、多くの場合ペットショップやブリーダーから購入すると言う方が多いのではないでしょうか。中には知り合いの家で生まれた子犬や子猫を譲り受けることもあるでしょうし、あるいは迷い犬や猫を保護して里親になるということもあるかもしれません。大切なことは、実際に動物を家に迎え入れる前に、その動物や品種に関してできる限りの情報を入手してしっかり準備をする、ということです。どのような飼育環境を用意したらよいか、食餌は何を与えるのか、ワクチンや予防などは何が必要か、など事前にしっかり予習しておきましょう。また、ペットショップでは判らないこともありますが、購入予定の子犬・子猫の親や兄弟に、遺伝的な病気などの発生がないかどうかも、きちんと聞いておくべきでしょう。良心的なブリーダーさんなら、きちんと詳細に教えてくれるはずです。
生まれて間もない小さな子犬や子猫はとても可愛いものです。しかし、まだ1回もワクチンを接種していないような幼若な動物は環境の変化に非常に弱く、病気に対する免疫も無いため、飼い始めて直ぐに具合が悪くなったり感染症に罹って死んでしまったりすることもあります。あまりに幼弱な動物を飼うことは非常に高いリスクを伴いますので、出来れば(犬や猫なら)ワクチン接種の済んだ2~3ヶ月齢以上の動物を飼うようにするのが安全です。
「動物病院」はペットを飼ってから行くところだ、と言うのが常識的な考えかもしれません。しかし大抵の動物病院では、「これからペットを飼いたい」という相談も、きちんと受け付けてくれるはずです。事前に電話などで問い合わせてから、相談してみると良いでしょう。
家族で生活している方の場合、「これは娘の犬だ」とか、「母の猫だ」という言葉を口にした経験はないでしょうか?例えば自分に「孫」が生まれると判ったとき、「あれは娘の子供だから自分は関知しない」という言い方をするでしょうか?ペットも本来「家族の一員」として受け入れられるべきであると、私は考えますので、家族全員が飼い主である、という認識を持って欲しいと思います。
【信頼できる獣医さんを見つける】
かかりつけの動物病院があって、信頼できる獣医師がいる、ということは、これから長い年月をペットと共に生活してゆく上でとても大切なことです。「良い獣医師」かどうかを、客観的に判断する基準は残念ながらありません。また、ある人にとっては「いい先生」でも、他の人にとっては「そうでもない」と言うこともあるでしょう。「良し悪し」の基準は人によって異なります。「じっくりと丁寧に説明してくれる先生」が良い、と言う人もいれば、「完結に解り易く言い切る先生」の方が安心できる、という人もいるでしょう。若くて気鋭の先生が良い、と言う人もいれば、年配のベテランの先生の方が安心感がある、という人もいるはずです。場合によっては「診療費が安い」ことが「良い病院」、という認識の人もいることでしょう。「人の噂」は有用な情報のひとつではありますが、100%信用せずに、自分の目で確かめることが大切です。特に初めてペットを飼うときは、幾つかの病院で「健康診断」などを受けてみて、自分とそのペットにとって一番相性が良いと感じた病院を「かかりつけ」にすると良いでしょう。
【「永遠の命はない」ということを理解する】
「命」には必ず「終わり」があります。私達がペットとして飼育する殆どの動物は、人間よりもずっと早く歳を取ります。逆に言えば、人間は非常に長寿の動物である、ということが出来ます。従って、私達人間は多くの場合、自分と生活を共にしてきたペットの最期を「看取る」運命にあります。「うちの子が死ぬときのことなんて想像したくもない」というのが一般的な意見かもしれません。もちろん、常にこんなことばかり考えていたら、確かに気が滅入ってしまいますね。しかし、永遠の命はありませんから、「そのとき」はいつか必ず訪れます。「この子の一生は自分のそれより短いのだ」ということを、心のどこか片隅に置いておくことで、限りある命の大切さを認識し、かけがえのない時間を大切にしよう、という気持ちが生まれてくるのではないでしょうか?
人間の子供の場合には、「生まれること」が判ってから実際に生まれて来るまでに数ヶ月という準備期間があります。その間に両親は、オムツの代え方からミルクの作り方、お風呂の入れ方、予防注射についてなど、いろんなことを「予習」するのではないでしょうか?これはペットの場合でも同じことだと思います。長い年月を共に過ごすパートナーに関することですから、事前の準備はいくらしても「し過ぎる」ということはありません。「ペットを飼いたいな」、そう思った瞬間から、準備期間は始まっているのです。
2004.10.01(金)
nikkansports(2004/9/27)
http://www.nikkansports.com/ns/general/f-so-tp0-040927-0003.html
共同通信
http://news.goo.ne.jp/news/kyodo/shakai/20040927/20040927a4990.html
《以下引用》
埼玉県に住む40代の男性が今年2月、飼っていたハムスターに指をかまれた直後に意識不明となり、搬送先の病院で死亡していたことが27日までに分かった。傷口からハムスターの唾液(だえき)が体内に入り、急激なアレルギー反応である「アナフィラキシー」が発生、持病のぜんそくを誘発したという。
ハムスターなどペットの齧歯(げっし)類にかまれたのが原因のアナフィラキシーは1995年以降、広島県など全国で17人報告され、16人は大事に至らなかったが、1人は植物状態になった。かまれた直後の死亡例は初めてとみられる。
診察した清田和也さいたま赤十字病院救命救急センター長は「常に起きるわけではないが、アレルギー体質の人や、かまれる危険の高い獣医師は気を付けた方がいい」と注意を呼び掛けている。(共同)
[2004/9/27/09:10]
《コメント》
「埼玉県に住む40代の男性が、飼っていたハムスターに噛まれてアナフィラキシーを起こし、死亡した」というのがニュースの内容です。記事によるとこの男性は、「持病の喘息」を持っていたようで、アナフィラキシーを起こしたことにより喘息発作を併発したために死亡したということのようです。
私たち獣医師にとっては、「ハムスターに噛まれるとアナフィラキシーを起こす可能性があるので危ない」というのは、実は非常に有名な話で、ペットを扱う獣医師なら誰もが知っていることです。ですから、ハムスターの診療をするときは結構緊張しながらしているんです、実は。
もちろんハムスターの唾液に猛毒が含まれている訳でも何でも無くて、これはハムスターの唾液に含まれる成分に対して人体が「アナフィラキシー」を起こすことでショックが生じるためにこのようなことが生じることが知られています。アナフィラキシーというのはつまり、急性に重度のアレルギーを起こすことで、軽いものなら蕁麻疹や「花粉症」に似たような症状で済みますが、重症になるとショック状態になり血圧低下や呼吸困難を起こすこともあり、もしもこれに喘息発作などが併発すれば、呼吸停止を起こして死亡する可能性は充分にあります。
アナフィラキシーはアレルギーの一種ですから、当然ながらハムスターの唾液に限らず様々なものにより引き起こされます。例えば蜂に刺されて重症になることがあるのも、「蜂の毒」によるのではなくて、「毒に対するアナフィラキシー」であると言われています。アナフィラキシーは食べ物に含まれるアレルギー物質で起こる事もあります。有名なところでは蕎麦、あるいは海老や蟹などの甲殻類も比較的強いアレルギーを起こすことがあります。そう言えば少し前のテレビ番組で、デートの前に海老を食べた男性とキスをしてアナフィラキシーを起こし、呼吸停止を起こした女性の話をやっていました。もしもこの女性が死亡してしまった場合、キスをした男性は「過失致死」となるのでしょうか?デートの直前に海老を食べたばっかりに・・・?
「犬や猫でも気を付けよう」などと書いてあるサイトなどもあるようですが、もちろんどんなものに対してもアレルギーが起こる可能性はあるし、動物に口移しで食べ物を与えたりするのは色んな意味でお勧めはしませんが、今のところ「犬や猫」で同様の事態が生じたという報告は、私の知る限りではありません。ですから、無闇に怖がる必要はありません。
2004.09.25(土)
● ストレスとは?
「現代はストレス社会だ」などという台詞をよく耳にします。「ストレス」という言葉を聞かない日がないくらい、この言葉は日常的なものとなっています。あらゆる病気が「ストレス」によって起こるとされ、まるで「悪者」の代表のように忌み嫌われているのが現状のようですが、では「ストレス」とは一体どのようなものを指すのでしょうか?
実は「ストレス」の定義は様々で、医学的に定まったものは無く、極めて抽象的な曖昧な言葉なのです。もともと「ストレス」という言葉は工学用語で、「金属に対して加えられた外力によって生じた歪みを元に戻そうとする応力」のことを言います。そしてこの「工学用語」を医学の分野で初めて使用したのが、カナダの病理学者のハンス・セリエ(1935年)です。セリエの「ストレス学説」によると、「ストレス」とは「外界からの侵襲に対して生体が適応する際の生体メカニズム」のことだそうです。そしてこの「ストレス」を引き起こす要因となる外的侵襲のことを「ストレス要因」、または「ストレッサー」と呼んだのです。
ここで「あれ?」と思われた方もいることでしょう。そうです。本来「ストレス」というのは「外的侵襲により引き起こされる歪み」に対する「適応メカニズム」のことであって、「歪み」そのものを指す言葉でないのです。従って、例えば「仕事での人間関係が上手くいかない」とか「恋愛のことで悩みがある」とか、「超多忙で心身が疲れる」とか、これらは全て「ストレッサー」であり、これらの刺激に対して体が「頑張ろう」とする適応反応を「ストレス」と呼ぶということになります。そして、「ストレッサー」による侵襲が、この適応反応の守備範囲を越えた場合に、頭痛や胃痛や、その他様々な症状を現して、「体を休めなさい」という警告を発するのだと考えられます。
ですから、「ストレスが溜まる」というような言い回しは、本来正しくないということになります。「ストレスの無い生活」というのはつまり、「適応反応を欠いた生活」ということであり、これでは生体が「生きて行く」ことができなくなります。
しかし、このように揚げ足を取ってばかりいても仕方がありません。日常的には、本来「ストレッサー」と呼ばれるべき外的侵襲や、これにより引き起こされる「歪み」そのものを「ストレス」と呼んでいるのが現状です。話がややこしくなってもいけませんので、ここではひとまず、現在一般的に使用されている語法、つまり「有害な外的侵襲」としての「ストレス」という言葉を採用し、以下のお話を進めることにしましょう。
● ペットにストレスが溜まるとどうなるのか?
ストレスが溜まる、つまり正確に言えば「ストレッサーによる刺激を受け続ける」ということですが、これは一体どのような変化を体にもたらすのでしょうか?
前出のセリエは、ストレスに対する生体適応反応により引き起こされる体の変化を「適応症候群」と名付け、さらにそれを「局所適応症候群」と「一般適応症候群」の2つに分類しました。そして「一般適応症候群」は更に3段階に分けられています。
細かく説明するとちょっと難しいのですが、簡単に言うと…
外的侵襲を受けると生体はまず、軽いショック状態となり、次いでこれに適応する為に血圧や体温を上げたり、副腎皮質ホルモンを分泌したりするようになります(第一期:警告反応期)。そして暫くは、この緊張状態が継続します(第二期:抵抗期)。よく「仕事が忙しいと気が張って風邪をひかない」などと言うことがありますが、この状態です。そしてこれを放っておくと、急激に抵抗力が低下して、体が悲鳴をあげ始める(第三期:疲憊期)、ということです。
人間の場合は、ストレスを引き起こす「ストレス要因」を、物理的要因、心的要因などに分類しています。犬や猫にとっては、生活環境の変化というのは非常に大きな「心的ストレス要因」となります。具体的には、引越し、家族構成の変化(結婚、出産など)、新しいペットの飼育、旅行に連れていく、ペットホテルに預ける、近所の騒音、家族(飼い主)の心理的変化やストレス状態、などが挙げられます。またお正月などに「親戚の子供達におもちゃのようにして触られる」などというのも、よくあるストレス要因です。
そしてこれらのストレス要因により様々な症状が引き起こされますが、特に犬で頻繁に見られる症状としては、下痢や血便、嘔吐などの消化器症状でしょう。また大型犬に多いと言われる「胃捻転・胃拡張症候群」も、ストレスにより引き起こされる傾向があります。また猫では、嘔吐や涎をダラダラ垂らすなどの消化器症状、血尿、膀胱炎などの泌尿器の疾患が発生することがよくあります。その他、抵抗力が低下することにより、肝臓病や各種の感染症、糖尿病などの内分泌疾患、腫瘍性疾患を引き起こす可能性があると考えられます。
● ストレスをためない為にはどうすればいいのか?
「ストレスは有害なもの」と仮定してここまでお話して来ました。しかし、本当にそうでしょうか?野生動物の場合、例えばライオンなどの肉食動物が獲物を見つけたとき、それを捕まえるために体が「狩の準備」をします。つまり、心拍数と血圧が上昇し、筋肉が緊張し、血糖値も上がるのですが、これが「ストレス」と呼ばれる状態の本来の姿です。獲物となったシマウマの方にも同様な反応が現れます。これはつまり、逃げる為に必要な「準備」です。このような「ストレス」は、動物が生きる為に必要なものです。
ストレスが全く無い状態とは、どのようなものでしょうか?人間で行われたある心理実験では、被験者が80~90時間、音も光も無い「無ストレス状態」に置かれると、ストレッサーに対する抵抗性を失って、色々な外的刺激に対して無力になってしまったそうです。また、産まれたばかりの赤ん坊を「無ストレス状態」で育てた実験(13世紀のお話です。酷い実験もあったものです。)では、赤ん坊全員が死亡してしまったそうです。
このように、ストレスは人間や動物が生きていく上で、ある程度必要なものであると言うことが出来ます。例えば盲導犬や介助犬が街で仕事をしている状態、しつけ教室などで訓練を受けているときの犬の状態は、軽いストレスを受けていると考えられます。徐々に慣らされた場合には、このような軽度のストレスが問題になることは殆どありません。しかし、過度なストレスは生体に有害な反応を起すことがあります。「ストレスを溜めない」とは、言い換えれば「過度なストレスによる有害反応を防ぐ」ということです。では、そのためにはどのようなことに注意すれば良いのでしょう?
神経質で臆病な性格の動物は、必要以上のストレスを感じるようになってしまいます。来客の際に吠える犬は、チャイムが鳴るたびに毎回ストレスを受けているのです。また爪切りや耳掃除が大嫌いな犬は、家や病院でこれらの行為をする度に大騒ぎとなり、自身も多大なストレスを受けることになります。犬にとって特に有害となるストレスの主な共通点は「恐怖」や「不安」です。「恐怖」や「不安」を避けるには、その原因となるような行為を「しないこと」が原則ですが、しかし来客や留守番、病院での治療行為など、人と共に生活する上で必要な事柄も少なくありません。従って、これらの行為に対して必要以上の恐怖感や不安感を抱くことが無いように、小さな頃から順応させるような「しつけ」をすることが重要と言えるでしょう。あまりに病的な場合には、専門家による行動療法が必要な場合もあります。
猫の場合は、なるべく複数で飼育しないことが重要です。猫は本来、単独で生活する動物なので、複数で飼育する場合には必ず、それぞれの縄張りを尊重してあげること、できれば別々の部屋で飼うこと、食餌の場所やトイレは必ず別々にすること(お互いの顔が見えないようにすること)が大切です。特に、相性の悪い猫同士を一緒に飼っているような場合、猫にとっては非常に大きなストレスを受けることになりますから、家に新しい猫を導入するような場合には細心の注意が必要です。
2004.09.13(月)
今回は以前から疑問に思っている「動物用シャンプー」に関する疑問を述べたいと思います。動物用シャンプーと言っても、シャンプーをする動物は主に犬なので、「犬用シャンプー」と言い換えても良いでしょう。
犬の皮膚のpHはヒトのそれとは異なり、弱アルカリ性だと言われています。本当にそうなのか?という疑問もあるのですが(犬の皮膚表面のpHを調べた文献はそれ程多くは無いため、根拠にはいまひとつ乏しい気がする)、そこから疑いだすと話が先に進まないので、とりあえずここまでは信用するとしましょう。
人のボディソープやハンドソープなどの業界では、暫く前から「弱酸性」ブームであることは周知の事だと思います。「人の肌は弱酸性、だから洗剤も弱酸性がお肌に優しい」と言われて、誰もが疑うことなく「その通りだ」と信じてしまっているようです。このような人たちに、「人の肌は弱酸性、同じpHの洗剤で洗うと肌に良くないので、弱アルカリ性がお肌に優しい」と言ってみたらどのような反応をするでしょうか?やっぱり「その通りだ」と信じてしまうのではないでしょうか?要するに、「それらしい宣伝文句」を使われれると何となくその気になってしまうものなのです。
これに関しては、以下のサイトが参考になります。
http://www.live-science.com/honkan/qanda/body10.html
つまり、「酸性」だろうが「アルカリ性」だろうが、洗剤はもともと肌に良くないので、必要最小限の汚れを落としたらきれいさっぱり洗い流した方がよい、というのが基本的な考え方です。汗や皮脂は酸性なので、弱アルカリの「石鹸」などで洗浄した場合、石鹸の界面活性効果は中和されて失活してしまうため、皮脂や角質を必要以上に取り去る事が無く、結果として皮膚に優しい、という事のようです。ところがこれを「弱酸性」のボディソープで洗うとどうなるかと言うと、同じ酸性どうしのため中和されないので、洗剤の界面活性効果は皮膚の表面で長時間作用してしまい、本来必要な皮脂や角質まで取り去ってしまう危険性がある、という訳です。この考えは、確かに一理ある、と思います。
で、これは犬でも全く同じように考えられる訳で、弱アルカリ性の皮膚を弱アルカリ性の洗剤で洗った場合、洗剤の界面活性効果はいつまでの残るため、皮脂や角質を必要以上に取り除いてしまう危険性がある、と考える事も出来ます。
しかしながら、動物用シャンプーのメーカーは何れも、「犬の肌は弱アルカリ性なので、シャンプーも弱アルカリ性が良い」と、当然の如く宣伝しているのが現状です。しかしなぜ「その方が良い」のか、誰も教えてくれません。とにかく「同じ方が良いに決まっている」ことになっているようです。
昔から、「ヒト用のシャンプーを犬に使用してはいけない」と言われ続けてきました。確かに、弱アルカリ性の石鹸を犬の皮膚に使用するのは、あまり良いことではないのかも知れません。しかし、弱酸性のボディソープ全盛の現在では、むしろヒト用の弱酸性洗剤を犬に使用する方が安全なのかもしれない?などと考えたりもしています。
どなたか、私の長年の疑問を解消してくださる奇特な方はいらっしゃらないでしょうか?
注意1 アレルギーや脂漏症など、特定の皮膚疾患を持っている動物ではそれぞれに応じた薬用シャンプーを使用すべきです。ヒト用のシャンプーは決して使用しないでください。
注意2 上記内容は、あくまで私個人が普段の診療で感じている疑問を紹介したに過ぎません。決して「犬にヒト用のシャンプーを使用する」ことを推奨している訳ではありませんので、これを実施して問題が起きたとしても私が責任を負うことは出来ませんのでご了承ください。
2004.08.22(日)
「獣医師の役割」とはひと言で言って何でしょうか?「動物の病気を治すこと」でしょうか?それとも「動物を何が何でも生かすこと」でしょうか?もちろん、獣医師の「仕事」は、病気の動物を診療して、診断して、治療することです。ですから、全ての動物の病気を「治す」ことが出来れば、言うことは何もありません。でも、中には現在の獣医療の水準では「治せない」病気もまだまだあります。またヒトと同様に、生きている動物は必ず寿命を迎えます。どうしても治らない病気に出会ったとき、あるいは老衰で動物が亡くなってしまったとき、獣医師は「役目を果たすことが出来なかった」ということになるのでしょうか?
牛や豚など、いわゆる「産業動物」の診療に携わっている獣医師の場合は、対象動物が病気になったとき、「病気を治すこと」だけではなく、経済的に採算が合うのかどうか、という「生産者の利益」まで判断に含めて診療を行います。例えば、乳牛が乳癌になっても乳房を切除することはありません。牛乳が出なくなってしまったら、乳牛の経済的価値がなくなってしまうため、お金をかけて治療する意義がないからです(余程血統が良ければ、繁殖用にする、ということもあるかもしれませんが・・・私は牛の診療はしたことが無いのでよく判りません)。
これに比較して、小動物:ペットの診療と言うのは、基本的に採算性は考える必要はありません。「ペットショップで10万円で買った犬だから、10万円以上の治療は受けさせない」なんて言う酷い(!)飼い主はいないでしょう(いないと信じてます)。そういう意味では、小動物の獣医療と人間の医療は、類似した性格を持っていると言ってよいでしょう。ですから、ここで「命題」にした「獣医師の役割」とは、広い意味では「医療提供者の役割」と言い換えることが出来ます。

では、「医療提供者」の究極的な役割、とは何でしょうか?
私は、ひと言で言うならば、それは「情報提供」だと考えています。もちろん手術もしますし、薬の処方もします。しつけの相談も受ければ食餌の相談をされることもあります。しかし、手術にしても病気や薬の説明にしても、一番大切なのは「正しい情報を提供すること」ではないでしょうか?例えば、一般的な手術であれば、「なぜこのような手術が必要なのか」「手術をしないとどのようなリスクが生じるのか」「手術をした場合のリスクはどのようなものがあるのか」「術後の生存率はどのくらいなのか」「手術以外の治療にはどんな方法があるのか」など、出来る限り詳細で正確な「情報提供」を、飼い主(ヒトの場合は患者自身)にすることが、これからの医療では非常に大切になってきます。ある手術を、「手術屋さん」というような「手術専門」の外科医に任せてしてもらった場合には、この外科医が行っているのは総合的な意味での「医療行為」ではなく、「医療技術の提供」である、と言うことが出来ると思います。もちろんこれが「悪い」と言っているわけではなく、ただ手術を行うだけでは「片手落ちである」ということを理解して頂きたいと思います。
私の知人の獣医師の一人は、「獣医師の究極的な役割は、動物を病気にさせないことだ」と言っていました。これもひとつの考え方ですし、否定するつもりはありません。しかし、では一体どうやったら「病気にさせない」ことが出来るのか?というのもひとつの「情報」だと思います。残念ながら、全ての動物を「病気にさせない」ことは、現実には不可能です。もしも病気にさせてしまったら、それは獣医師が役割を果たさなかった、ということになるのでしょうか?多分そうではないでしょう。「病気にさせないこと」は、「役割」というよりは、「理想」あるいは「目標」のようなものと言うべきでしょう。
インターネットなどのお陰で、私たちの周りは様々な「情報」で溢れかえっています。動物の病気や健康に関連した情報も、ネットで検索をかければたちどころにいろんな情報を入手することが出来るようになりました。中には非常に役に立つものも沢山あります。しかし、○○は体に良い、■■は良くない、××を飲んだらどんな病気でも治る、△△でアトピーが治った、◎◎で癌が治った・・・。このような「商品販売」を目的としたような、信憑性のない「情報?」もまた少なくありません。私達「(獣)医療提供者」には専門家として、これら玉石混淆の「情報」の中から、どれが「正しい」情報で、どれが「間違った」情報で、どれが「怪しい」情報なのかを、科学的・論理的に判断して、飼い主(患者)に開示する、という役割があると考えます。
幾ら高価な道具・機器があっても、それを有効活用し診断・治療に結びつけ、より良い結果を生むためには、「正しい情報」が必要です。インフォームドコンセント、インフォームドチョイスとは、「正確な情報提供」なしには実践できません。そして、莫大な量の「情報」を整理して有効に利用する能力が、(獣)医療提供者にとって、今後ますます重要になってくるに違いありません。