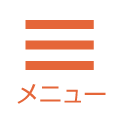ブログ・コラム
Blog2017.11.02(木)
■不妊手術とは?
不妊手術とは、繁殖により子孫が生まれないようにするための手術で、一般的に雄の場合なら「去勢手術」、雌の動物なら「避妊手術」と呼ばれています。動物を「繁殖」目的で飼育する場合以外は、不妊手術を実施するのが一般的です。犬と猫の場合に於ける、不妊手術のメリットとデメリットに関しては、こちらを参考にしてください。

■不妊手術の方法
雄の場合の不妊手術(去勢手術)では、両方の精巣を切除します。陰嚢またはその直ぐ上の皮膚を切開し、精巣を露出させて血管と精索という管を糸で結紮して、摘出します。切開した皮膚は縫合して閉じます。猫の去勢手術の場合は、切開した陰嚢の皮膚の収縮が早く、縫合の必要が無い場合もあります。
精巣はもともとお腹の中にあったものが、生後数週間(場合によっては数ヶ月)の間にお腹の外=陰嚢に降りてきます。しかし、ときおり精巣がお腹の中に留まったまま、成長が終わっても降りてこない場合があります。このような状態を「潜在精巣」と呼びます。お腹の中に残った精巣は、そのままにしておくと、数年経ってから「腫瘍化」する可能性が高く、「セルトリ細胞腫」という悪性腫瘍が発生した場合には、腫瘍細胞から過剰に分泌されるエストロジェンにより骨髄抑制が起こり、不可逆性の貧血・血小板減少症を引き起こして命を落とす場合があります。このため、潜在精巣が判明している場合には早期にお腹の中に残っている精巣を摘出することが推奨されます。
精巣が、お腹の外には出ているけれど、陰嚢には到達していない、というケースもあります。多くの場合はソケイ部などの皮下に留まっている事が多く、この場合も正常な精巣に比較すると腫瘍化するリスクは大きいと考えられるため、早期に摘出すべきと考えられます。
雌の場合は、 卵巣だけを摘出する方法と、卵巣および子宮を摘出する方法と、大きく2通りの方法に分けることが出来ます。一昔前までは、卵巣だけを摘出する方法が主流でした。その後、卵巣だけを摘出して子宮を残すと、残った子宮が蓄膿症になるなどの説が広まり、現在では「卵巣および子宮」を摘出する方法が一般的となっています。ところが、繁殖学の専門家の最新の知見では、「健康な子宮は切除せずに残しておいても、蓄膿症などの合併症を起こすことは理論的にあり得ない」とされているのです。つまり、卵巣だけの摘出でも全く問題が無い、とうことが判って来たのです。
しかしながら、現在日本国内では「卵巣子宮摘出」が主流です。またアメリカなどの海外でもこの方法が主流となっているようです。その理由として、「卵巣摘出では卵巣の取り残しを起こす確立が高い」というのが一番に挙げられるようです。アメリカは訴訟社会ですから、切除したはずの卵巣を取り残して、子宮蓄膿症などの合併症を起こした場合には、獣医師の責任が大きく問われる事になります。このため、より確実に大きく切除して取り残しが無いようにする方法として、卵巣子宮摘出術が多く採用されている、という実情があるようです。日本の獣医学はアメリカの影響を強く受けているため、日本でも同様の方法が一般的になっているものと考えられます。
当院では、上記の「健康な子宮は切除せずに残しておいても、蓄膿症などの合併症を起こすことは理論的にあり得ない」と言う最新の考え方を採用し、特別な理由が無い限り「卵巣だけの摘出」を行っています。
過去数年間にわたり卵巣摘出を100例以上で実施しておりますが、取り残しや子宮蓄膿症などの合併症を起こしたケースは1例もありません。反対に、(他の病院で)卵巣・子宮摘出を実施されていたケースで、子宮の結紮/切除部位に膿瘍や縫合糸に対する異物反応を起こしたため開腹による切除が必要となった症例や、子宮の切除が不十分で、いつまでも陰部からの粘液分泌が続いて治まらなかった症例などを幾つも経験しています。このような事も考え合わせると、卵巣だけの摘出は合併症も少なく、そのメリットは大きいものと思われます。
例外的な注意として、将来「乳腺腫瘍」が発生し、性ホルモンとしての作用を持つある種の抗癌剤を使用した場合、残した子宮が蓄膿症を発生する可能性があります。しかし、乳腺腫瘍に対して抗癌剤を使用することがそれ程一般的ではないこと、さらにこの抗癌剤は副作用が強く効果も一定ではないため、動物での使用は極めて限られている事、などから、この薬剤使用による合併症の発生は、リスクの大きさとしては非常に小さなものと考えられます。
不幸にして、残した子宮に腫瘍などの疾患が発生する可能性もゼロではありません。そこに「細胞」がある限り、腫瘍が発生する可能性を否定できるものではありません。しかしながら、その可能性はその他の臓器や組織に腫瘍が発生するリスクと同等のものであり、これを防ぐために子宮を切除するというのは例えば、極端に言えば「骨肉腫が出来るといけないので健康な足を切断する」とか、「血管肉腫ができるといけないので健康な脾臓を摘出する」と言うのとあまり変わらない発想になります。
「それでも卵巣と子宮を取って欲しい」というご希望がある場合には、もちろん「卵巣・子宮摘出」を実施しております。
※Ohio State Universityの獣医軟部外科専門医Dr.Smeakとの会話も参考になります。
■不妊手術はいつすれば良いか?
「去勢手術」「避妊手術」はいつ頃すればよいのか?と言うのはよく受ける質問です。これは「何を目的とするか」により、適切な時期が異なります。
単に「繁殖を防ぐため」だけであれば、時期はいつでも構いません。繁殖してしまう前に手術を受ければよいでしょう。また「攻撃性」などの問題行動を防ぐ目的ならば、なるべく早期に不妊手術をすべきです。最近のアメリカでは、子犬や子猫がまだかなり小さいうちに手術をしても、特に大きな問題はない、という考え方もあるようです。しかし日本では習慣的に、あまり小さな子犬や子猫に全身麻酔をかけて手術を行うことはされていません。当院でも、特別な理由が無い限り、生後2ヶ月以内の動物に全身麻酔をかけて手術する事は出来る限り避けるようにしています。
一番問題になるのは、雌の犬における「初回発情」との時期的な兼ね合いでしょう。初回発情(生理)が来る前に避妊手術を実施すると、将来的に乳腺腫瘍の発生率が低くなる、というデータがあります(※)。このため、生まれて最初の発情が来る前に避妊手術を行うのが効果的であると言われています。早い個体では生後5ヶ月齢くらいで初回の発情が来てしまうこともあるため、4-5ヶ月齢のころには手術を考えた方がよいかもしれません。もちろん、手術前に発情が来てしまったら絶対に将来乳腺腫瘍が発生する、と言うわけではありません。たとえ何度か発情を経験してしまった後に手術した場合でも、避妊手術をしない場合と比較すると乳腺腫瘍の発生率はやや低くなると言われています。猫の場合も、(犬の場合ほどはっきりした関連性は見られませんが)避妊手術をした猫の方が、手術をしていない猫よりも乳腺腫瘍の発生率が低い、と言われています。
つまり、特に雌犬の場合は、「乳腺腫瘍」の問題に拘るのなら、生後4-5ヶ月くらいで避妊手術をすることを考える、それ以外の場合は、ある程度成長が終わった時点(1歳前後)で手術を考えるのが、現段階では適切ではないかと思われます。
※ 追記(2013年9月);近年、雌の不妊手術の実施時期と乳腺腫瘍の発生率との因果関係が曖昧になりつつあります。世界中の信憑性のありそうな文献を調査した結果、今まで考えられていたほどには明確な関連性は確認されなかった、という文献が発表されました。詳しくは院長のブログをご覧ください。
2017.11.02(木)
▽ノミの被害と生活環
ノミと一口に言っても、実は幾つかの種類があります。基本的には、イヌノミは犬に寄生し、ネコノミは猫に寄生し、人にはヒトノミが寄生する、と考えられていました。ところが数年前の調査により、ネコノミは猫のみならず犬や人などにも寄生することが知られるようになり、犬や猫などのペットに寄生しているノミの多くが、実は「ネコノミ」であるということが判明しています。
ノミによる被害としては、まず吸血による皮膚炎が挙げられます。ノミに刺されると、非常に強い痒みが生じます。またノミに対してアレルギーを持っている場合には、刺された部位だけではなく全身に痒みが生じる場合もあり、少数の寄生でも非常に重い症状が現れることも珍しくありません。激しい痒みのために皮膚を掻き壊して出血したり、睡眠不足になったりする可能性もあります。犬や猫に寄生したノミ(特にネコノミ)がヒトにも一時的に寄生して被害をもたらすこともあります。また、ノミは条虫(サナダムシ)を媒介することでも良く知られています。動物の糞便に混じって環境中に排泄された条虫の卵は、ノミの幼虫に食べられます。条虫の幼生を体内に宿したまま、やがて成虫になったノミは犬や猫の皮膚に寄生し、痒みのために動物が皮膚を舐めたり齧ったりした拍子に口から飲み込まれてしまいます。飲み込まれたノミの体は胃の中で消化されてしまいますが、条虫はそのまま動物の小腸に寄生して成長する、というのが条虫のライフサイクルです。つまり、条虫が寄生していたら必ずノミがいる(いた)ということになります。
ノミの成虫は寄生している動物の体表で産卵しますが、卵は外界に落下して孵化します。したがって、動物の寝床などが「ノミの巣」になっていることがよくあります。ノミの幼虫は主に成虫の糞を食べて大きくなり、やがて蛹から成虫になって、再び犬や猫に寄生します。
▽ノミの予防と対策
ノミの生活環を見ても判るように、ノミを駆除するためには動物の体表についた成虫を駆除するだけでは不十分です。すでにノミが多数寄生しているような場合は、その動物の寝床にはノミの幼虫や蛹が大量に生息している可能性が高いので、ノミ取りシャンプーや成虫駆除剤では一時的な効果しかなく、まして「ノミ取りグシ」で1匹1匹捕まえても殆ど意味がありません。
ノミの場合も、被害に合ってから慌てて対策を考えるよりも、予防する方がずっと楽でもあり、重要なことです。ノミの予防薬は「成虫駆虫薬」と「繁殖予防薬」に分けることができます。成虫駆虫薬は字のとおり、寄生した成虫を駆除する薬で、皮膚に滴下するスポットタイプのものなどが一般的です。繁殖予防薬というのはノミの卵が孵らないようにする薬のことで、これには飲み薬のタイプと、スポットタイプの成虫駆虫薬と合剤になっているものものがあります。合剤になっているものは、成虫の駆除と繁殖予防が同時にできます。すでにノミの被害が発生している場合には、成虫駆虫薬と繁殖予防薬を併用するとともに、環境中の幼虫や卵を駆除する必要があります。ノミは湿度の高い環境を好むので、風通しを良くして乾燥させることが大切です。また動物が寝床として使用していたタオルや毛布などを新しいものに取り替えたり、スプレー式のノミ駆除剤やバルサンなどの殺虫剤を使用することもある程度有効でしょう。
ノミは既にノミを持っている動物と接触したり、ノミに汚染された環境に立ち入ることで感染しますが、完全室内飼育だからと言って安心することはできません。全く予防をしていない場合には、ほんの少数の寄生が甚大な被害に拡大する危険性もあります。特に梅雨時から夏場の高温多湿の時期は、しっかりノミの予防をすることが大切です。
▽マダニの被害と対策
ノミに次いで重要な外部寄生虫がマダニです。マダニは犬や猫などの皮膚に寄生し、頭の一部を皮膚の中に突っ込んだ状態で吸血します。血液を一杯に吸い込んだマダニは、直径が1cmくらいになることもあり、放っておくとやがて落下して野外で産卵します。草むらで孵化したマダニの子供は丈の高い草に登りながら成長し、徐々に草の先端に移動します。そして犬や猫、ヒトなどが傍を通りかかったときにその体表に移動して寄生します。
マダニの被害としては、大量寄生により貧血を起こしたり、ある種のウイルスやリケッチア、血液寄生性原虫などの病原体を媒介することもあります。また動物が掻いたり舐めたりした拍子に皮膚に食い付いていたマダニの胴体が取れてしまい、頭部だけが皮膚の中に残って化膿する場合もあります。慣れない人が、動物の皮膚に寄生してるマダニを見つけて「もぎ取る」と、これと同じことが起きて化膿する場合があるので、マダニを見つけたときには動物病院で取ってもらうことをお勧めします。
マダニの駆虫・予防はノミの対策と同様、皮膚に滴下するスポットタイプの薬剤が一般的です。ノミの成虫駆虫薬の中にはマダニを同時に駆除できるものもありますので、特に野外に出る機会の多い犬や猫ではしっかり予防することが大切です。
2017.11.01(水)
▽ワクチンの種類
猫のワクチンは「3種混合」が主流でしたが、最近では4種、5種というものが出ています。3種混合ワクチンには以下の病気に対するワクチンが含まれています。
1.猫伝染性鼻気管炎(FVR)
2.猫カリシウイルス感染症(FCV)
3.猫汎白血球減少症(猫パルボ;FPV)
この3種を中心として、猫白血病ウイルス(FeLV)のワクチンを追加したものが4種混合、さらにクラミジアのワクチンを追加したものが5種混合になります。FeLVのワクチンはそれだけ単独のものがありますが、クラミジア単独のワクチンは現在のところ日本にはありません。
また2008年7月より猫エイズウイルス(FIV)感染症に対するワクチンが接種可能になりました。ただし、当院では現在のところ性急な導入を見合わせております。
▽ワクチン接種の必要性
FVRやFCVは屋外の猫では非常に頻繁に見られるウイルス感染症です。FVRは激しい鼻炎や気管支炎、結膜炎、角膜炎を引き起こします。子猫ではこびり付いた目ヤニで目が開かなくなってしまったり、著しい角結膜炎のため瞼と眼球の角膜が癒着してしまうこともあります。FCVはFVRと似たような症状を示すものもありますが、口内炎や舌炎を起こすことで知られています。どちらもそれだけでは致死的ではありませんが、体力の無い子猫の場合には、脱水や栄養不良などを引き起こして死亡してしまう可能性もあります。これらのウイルスは感染力が非常に強く、一度感染すると慢性化することが多いため、ワクチンでしっかり予防することが大切です。
FPVは最近ではあまり見かけなくなりましたが、地域によってはまだ多くの発生が見られるところもあります。この感染症にかかると激しい嘔吐と水様性の下痢を起こし、白血球減少症を引き起こします。非常に死亡率の高い怖い病気なので、ワクチンで予防することが推奨されます。
完全室内飼育の猫でも、たまたま脱走してしまったり、外猫が室内に侵入してきたり、あるいは飼い主自身が外で感染猫に触ってウイルスを持ち込んでくることもあるため、決して感染の機会が無い、という訳ではありません。室内、屋外飼育を問わず、3種混合ワクチンは全ての猫で接種すべきである、と考えてよいでしょう。
FeLV;猫白血病ウイルスは、FeLVに感染した猫に噛まれたり、傷を舐め合ったりなどの濃厚接触をすることにより感染します。このウイルスに感染すると、白血球減少症を起こしたり、リンパ腫などの腫瘍性疾患を発症するリスクが高くなります。ワクチンを適切に接種することで感染率を減少させることができますが、このワクチンは(特に海外で)接種部位にしこりが出来たり、そのしこりが悪性腫瘍化する※という副作用が報告されています。通常、動物のワクチンは背中の肩甲骨の間に接種するのが普通ですが、ここで悪性腫瘍が発生すると、手術により切除するのが非常に困難になってしまいます。そのため、FeLVワクチンを接種するときは背中ではなく、後ろ足や尻尾の先に注射することが推奨されています。これは、万が一接種部位に腫瘍が出来たとしても、後ろ足または尻尾を切除することでその猫の命を救うことができるからです。
※上記の「ワクチン接種部位肉腫」ですが、以前はFeLVワクチンや狂犬病ワクチンなどの不活化ワクチンのみで発生すると考えられておりましたが、猫では3種混合ワクチンをはじめあらゆる(ワクチン以外の)皮下注射でもこのような状況が生じる可能性がある、ということが判明してきており、そのため当院では3種混合ワクチンの場合も後肢の膝より遠位の皮下に接種するようにしています。
FeLVのワクチンは「屋外で飼育されており、よく喧嘩して来る」など、FeLVに感染する確立の高い猫にだけ、必要に応じて接種するのが最良の方法である、というのが当院の考え方です。
▽ワクチン接種プログラム
生まれたばかりの仔猫は、免疫系が未発達なので、自分で免疫抗体を作ることができません。抗体を作れるようになるまでは、母親の初乳に含まれていた移行抗体という免疫抗体によって様々な病気から守られています。この移行抗体は、生後約8週間目くらいから徐々に減少し始め、12~13週間目くらいでほぼ消滅します。
この時期、仔猫も徐々に自分で抗体を作れるようになって来ますが、移行抗体は減少するため感染を防御する能力も次第に弱くなってきます。従ってこの時期に最初のワクチンを接種する必要があるのですが(「ワクチンを打つ」ということは、「自分で抗体を作らせる」ということです)、ここで問題が一つあります。移行抗体が仔猫の体に残っていると、ワクチンを接種しても、きちんと抗体を作ることができません。ですから、この期間、病気から仔猫を守り、最終的に、ワクチンによってしっかりと抗体が作られるようにしなければなりません。そのためには、移行抗体が減少し始める8週目くらいから完全に無くなってしまう13週目までの間に数回にわたってワクチンを接種するのが最も効果的です。
このようにして考えられたワクチンの打ち方(いつから、どのくらいの間隔で、何回打てばよいか)を、ワクチネーション・プログラムといいます。 ワクチネーション・プログラムは、仔猫の生活環境やワクチンの種類などによりいくつかの方法がありますが、通常は、生後2カ月目(約8~9週)と3カ月目(12~13週)に1回づつの計2回接種する方法が一般的です。そして次の年からは、年に1回づつ接種するのが理想的です。
初年度のワクチネーション・プログラムにより得られた免疫は、約1年間効果が持続しますが、時間がたつと次第に効果が落ちてきます(「抗体価が下がる」といいます)。1年に1回ワクチンを追加接種することにより、下がってきた抗体価を再び上昇させ、感染に対する免疫力を高めることができます。これをブースター効果と言います。 初年度のワクチネーション・プログラムの最後のワクチン接種(12~14週目)後1-2週間(免疫の効果が出始める)は、感染の危険性のあるような場所に連れ出したり、他の猫と接触させたりしないようにすることが大切です。
▽猫のワクチン接種は3年に1回でよい?
数年前から「猫のワクチン接種は3年に1回で充分」という噂?が広まっているのをご存知かもしれません。これは、アメリカの猫内科学会および米国猫臨床医協会が2000年に出した報告した推奨プログラムが元になっているのですが、実はアメリカと日本では状況が異なります。アメリカでは、日本で主流となっている3種・4種に加えて狂犬病ワクチンやクラミジア(これは最近日本でも発売されましたが)、FIP(猫伝染性腹膜炎)、FIV(猫エイズ)など、非常に多くのワクチンが出回っており、これら全てを毎年接種することは経済的にも猫自身の身体的にも非常に負担が大きくなる、との考えが根底にあります。従ってそれぞれのワクチンは3年に1回でも、結局ローテーションで毎年何らかのワクチンを接種していることになるのです。
日本で製造・販売されているワクチンは全て、「1年に1回の接種」で認可が下りています。従って、3年に1回の接種で万が一FVRやFCVに感染・発症したとしても、メーカーとしては何の保障もしてくれません。また殆どの場合、動物用の保険にも加入することができません。ペットホテルやペット同伴可の宿泊施設などでも、年に1回のワクチンを接種していない場合には宿泊を断られるのが普通です。
また日本では、アメリカに比べてワクチンの接種率そのものがまだまだ低いのが現状です。全国の猫の飼育頭数に対するワクチン接種率が低いと、免疫の保持率のばらつきが大きくなり、集団としての免疫保有率が低下してしまいます。現状でも「集団免疫」としての役割を十分果たすだけのワクチン接種率に達していない状態で、更にワクチン接種の機会を減らす方向性を日本で推奨することは、今の段階では危険性が高いのではないか、と考えられます。もちろん、ワクチン接種率そのものが高くなり、皆が確実に3年ごとにワクチンを接種する、と言う状況になれば、それが最も理想的な状況ではあります。将来的には、日本でも安心してこのような接種プログラムが可能になると良いと思います。
以上のようなリスクやデメリットを了承した上で、それでも3年に1回の接種にしたい、という方もいるかもしれません。もちろんこれらの混合ワクチンは、「犬の狂犬病ワクチン」のように法律で定められたものではありませんので、自己の責任に於いてよく考えながら判断されることをお勧めします。
▽ワクチン接種後の注意
猫の場合も、犬と同様にワクチンを接種した後にアレルギーなどの副作用を起こす可能性があります。注意点としては犬の場合と基本的に同様ですので、こちらを参考にしてください。
2017.11.01(水)
▽ワクチンの種類
現在、複数の製薬会社から様々な種類の混合ワクチンが市販されていますが、一体「何種混合ワクチン」を接種したらよいのか迷ってしまうことも多いのではないでしょうか?ここではまず簡単にワクチンの種類について説明したいと思います。
まず、5種混合ワクチンを基本として考えて見ましょう。「5種」とは次の5種類のウイルス病を指します。
1.ジステンパーウイルス感染症
2.アデノウイルス I 型感染症(犬伝染性肝炎)
3.アデノウイルス II 型感染症
4.パラインフルエンザ感染症
5.パルボウイルス感染症
この中で、ジステンパーと伝染性肝炎、パルボウイルス感染症は特に重症度が高く、子犬では感染により死亡することも珍しくないため、「コアウイルス」として非常に重要になります。アデノにはI型とII型がありますが、実際には片方のワクチンで2種類の病気が予防できるので、通常はII型1種類が入っていますので、4種の成分で5種類の病気が予防できる、というのが5種混合ワクチンです。そして5種混合にコロナウイルスが追加されたものが6種混合ワクチンです。コロナウイルスは、単独感染ではそれ程重症にはなりませんが、パルボウイルスと重複感染すると、パルボによる致死率が上昇すると言われています。しかし、生後6週齢を過ぎた犬では殆ど感染せず、してもあまり大きな問題にはならないことが多いとも考えられています。
これら5種・6種のワクチンに「レプトスピラ感染症」のワクチンを追加したものが8種・9種・10種などの混合ワクチンです。レプトスピラ症には幾つかの種類(血清型)がありますが、どの血清型が何種類入っているかはワクチンメーカーにより異なっています。2017年12月現在、入手できるもっとも多価のワクチンは10種混合ワクチンで、これは6種のウイルス疾患と4種類の血清型のレプトスピラを予防できるワクチンです。
レプトスピラはウイルスではなく、スピロヘータ属というラセン菌の一種で、ネズミやモグラその他の野生動物から犬やヒトに感染します。人畜共通感染症のため、盲導犬や介助犬など一般のヒトと接触する機会の多いアシスタントドッグでは、9種以上の混合ワクチンの接種が推奨されます。また、猟犬や、頻繁に野外に連れ出す機会の多い犬では、レプトスピラを含んだワクチンを接種する必要性が高くなります。
当院ではこれまで㈱微生物化学研究所(京都微研)の5種および11種ワクチンを使用しておりましたが、同社が犬・猫のワクチン製造から撤退したため現在はZoetis社の6種および10種ワクチンを採用しております(今後も諸般の事情により変更される場合がありますのでご了承ください)。6種と10種どちらのワクチンを接種するかは、その子の年齢(月齢)や生活環境などにより異なります。詳しくは病院スタッフ、獣医師にご相談ください。
▽ワクチン接種の必要性
ワクチンを接種しても、病気を100%防げるわけではありません。 しかしながら、パルボやジステンパーなど、感染すると死に至るかもしれないような怖い病気に対して、ワクチンを接種して免疫を高めておくことは決して無意味なことではありません。 これらの病気は特に、子犬での致死率が高く、若い犬では接種の必要性が高くなります。また、ワクチンを接種していない母犬から生まれた子犬は、母乳からこれらの病気に対する「移行抗体」をもらうことが出来ないため、パルボやジステンパー、その他の感染症に罹る危険性が高くなります。
特定の地域や集団内でのワクチン接種率が高いと、病気に対する集団全体としての抵抗力が強くなり、たとえその集団内に「ワクチン未接種の子犬」などの「感受性の高い個体」がいたとしても、病気に感染する確立が低くなると言われています。これを「集団免疫」と言います。つまり、ワクチンを接種するということは自分自身の身を守るだけではなく、間接的に「抵抗力の弱い」身近な子犬達を病気から守ることにも繋がるのです。
このように、ワクチンは適切に接種することが大切です。

▽ワクチン接種プログラム
生まれたばかりの仔犬は、免疫系が未発達なので、自分で免疫抗体を作ることができません。抗体を作れるようになるまでは、母親の初乳に含まれていた移行抗体という免疫抗体によって様々な病気から守られています。この移行抗体は、生後約5週間目くらいから徐々に減少し始め、12~14週間目くらいでほぼ消滅します。
この時期、仔犬も徐々に自分で抗体を作れるようになって来ますが、移行抗体は減少するため感染を防御する能力も次第に弱くなってきます。従ってこの時期に最初のワクチンを接種する必要があるのですが(「ワクチンを打つ」ということは、「自分で抗体を作らせる」ということです)、ここで問題が一つあります。移行抗体が仔犬の体に残っていると、ワクチンを接種しても、きちんと抗体を作ることができません。ですから、この期間、病気から仔犬を守り、最終的に、ワクチンによってしっかりと抗体が作られるようにしなければなりません。そのためには、移行抗体が減少し始める5週目くらいから完全に無くなってしまう14週目までの間に数回に渡ってワクチンを接種するのが最も効果的です。
このようにして考えられたワクチンの打ち方(いつから、どのくらいの間隔で、何回打てばよいか)を、ワクチン接種プログラムといいます。ワクチン接種プログラムには、仔犬の生活環境やワクチンの種類などによりいくつかの方法がありますが、次のようなプログラムで接種します。
1. 生後2カ月目(約8~9週)と3カ月目(12~14週)にそれぞれ1回づつの計2回接種
2. 生後6週目と9週目、更に12~14週目に1回ずつの計3回接種
そして、次の年からは、1年に1回づつ接種するのが理想的です。 初年度のワクチネーション・プログラムにより得られた免疫は、約1年間効果が持続しますが、時間がたつと次第に効果が落ちてきます(抗体価が下がる)。1年に1回ワクチンを追加接種することにより、下がってきた抗体価を再び上昇させ、感染に対する免疫力を高めることができます。これをブースター効果と言います。
レプトスピラ感染症の発生地域付近に済んでいる場合や、夏休み・お正月などに「発生地域」に旅行・帰省するような場合には、出来れば半年に1回、レプトスピラのワクチンを接種することをお勧めします(レプトスピラ単独のワクチンは通常在庫していないこともありますので事前にご確認下さい)。
初年度のワクチネーション・プログラムの最後のワクチン接種(12~14週目)後1~2週間(免疫の効果が出始める)は、感染の危険性のあるような場所(屋外や犬の集まる所など)に連れ出したり、他の成犬と接触させたりしないようにすることが大切です。
▽ワクチン接種後の注意
ワクチン接種後に何らかの副反応が出る場合があります。ワクチン接種後の反応としては、注射した局部の腫れやしこりなどの他、顔が腫れたり、急に元気が無くなったり、虚脱してショック状態になることもあります。「アナフィラキシー」という非常に強いアレルギー反応を起こした場合には、非常に稀ではありますが、命に関わる危険性も出て来ます。今まで何でも無かったからこれからも大丈夫、と言い切れるものではありません。
急性の強いアレルギー反応は通常、接種後短時間(30分~数時間程度)で発生することが多いため、病院でワクチンを接種した後は、できれば1時間くらい病院内で様子を見てから帰宅されることをお勧めします。したがって、夕方接種して夜間に具合が悪くなるという状況を避けるため、可能な場合は出来るだけ午前中にワクチンを接種することをお勧めしています。また、ワクチンを接種した日はあまり興奮させたり、激しい運動をさせないように注意してください。万が一、様子がおかしい時はすぐに病院に連絡してください。
2017.11.01(水)
▽ フィラリアのライフサイクル
「フィラリア」とは犬や猫などの心臓(猫の場合は主に肺動脈)に寄生する、体長10~15cm程度の細長い形をした「寄生虫」の一種です。 フィラリアは、フィラリアの感染子虫を持った「蚊」に刺されることにより感染します。犬や猫の心臓に寄生したフィラリアの親虫は、「ミクロフィラリア」と呼ばれる小さな子虫(この子虫は顕微鏡でしか見ることができません)を産みます。ミクロフィラリアは血流に乗って全身の血液中に行き渡りますが、この血液を蚊が吸血することによりミクロフィラリアも一緒に蚊の体内に吸い込まれることになります。ミクロフィラリアは蚊の体内で成長し、やがて「感染子虫」と呼ばれる状態になります。そして蚊が再び吸血のために動物の皮膚に「針」を刺して穴を開けると、感染子虫は蚊の体内から脱出し、皮膚に開いた穴から動物の体内に侵入します。体内に侵入したミクロフィラリアは脱皮・成長を繰り返しながら、数ヶ月後には心臓に到達し、そこで再びミクロフィラリアを生むようになります。
▽フィラリア症の症状
フィラリア症の症状は主に、心臓に寄生した親虫により引き起こされます。寄生している虫の数により症状の重症度が多少変わりますが、多数の虫が寄生している場合には重度の心不全を引き起こし、様々な症状が見られるようになります。典型的な症状としては、
1)腹水が貯まってお腹が膨れる
2)呼吸が苦しく、咳が出る事もある
3)疲れやすい、散歩中などに倒れる
4)心臓発作、死亡
などを挙げることが出来ます。フィラリア虫体が肺動脈から右心室-右心房を乗り越えて後大静脈にまで到達した状態を「ベナケバ症候群」と呼びますが、この状態になると特に重い症状が見らるようになり、赤黒い尿が見られることもあります。

▽フィラリアの検査
フィラリア予防薬は原則的に、フィラリアの寄生が無い状態で投与するのが基本です(既に寄生している場合には、保存的治療と併用して予防薬を投与する場合もありますが、ある程度のリスクを伴う事になります)。通常は、毎年の予防を始める前に、フィラリアの検査を実施することが薦められます。フィラリアの検査には、ミクロフィラリアを検出する方法と、親虫の抗原を検出する方法があります。親虫が多数のミクロフィラリアを生んでいる場合には、血液をほんの1滴スライドグラスに垂らして顕微鏡で観察するだけで簡単にミクロフィラリアを確認する事ができます。しかし、親虫の寄生期間が短い場合や「雄」の親虫しか寄生していない場合、あるいは検査をせずにフィラリア予防薬を投与してしまった後などでは、たとえフィラリアが心臓に寄生していてもミクロフィラリアが検出できない場合があります。そこで、より確実にフィラリアの寄生を確認する方法として、血清学的にフィラリア虫体の抗原を検出する、と言う方法があります。
▽フィラリアの予防
フィラリアは、外科的に摘出したり、駆虫薬を投与して心臓に寄生している親虫を殺滅したりなどの「治療法」を選択する場合もありますが、いずれの場合も非常に高いリスクを伴う「治療」となります。「治療」行為により余計に状態が悪化したり、最悪のケースでは死亡してしまうような危険性も指摘されています。従って、フィラリアは「罹ってから治療する」のではなく、「罹らないように予防する」のが基本となります。通常1ヶ月に1回、予防薬を飲ませる事で、ほぼ確実にフィラリアを予防する事が出来ます。予防の期間は地域などにより多少異なりますが、当院では5月下旬から11月下旬まで、毎月予防することをお勧めしています。