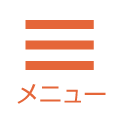ブログ・コラム
Blog2017.11.02(木)
手術の際には通常、最後に皮膚を縫合します。普通はナイロン糸などの「非吸収性・モノフィラメント」の糸を使用しますが、ステープラー(皮膚縫合用ホチキス)などを使用する場合もあります。
一昔前までは、縫合した術創を毎日イソジンなどの消毒液で消毒する、というのが「常識」でしたが、現在はそのような行為には意味が無いということが判っており、退院後に毎日傷口の消毒をして頂く、などということはありません。むしろ、消毒をすると傷の治りが遅れる可能性があるため、縫合した術創の消毒は「してはいけない」というのが現在の常識です。
動物の場合は、縫合創を舐めたり齧ったり、引っかいたりして、縫った皮膚が開いていしまったり糸が取れてしまったりすることがあります。このような事態を防ぐため、術後数日間はエリザベスカラーや腹帯(術後衣)などを利用して、傷を舐められないようにするなどの必要があります。しかし、術創をそれ程気にしない動物の場合には、軽く包帯を巻いたり、T-シャツなどを着せて傷を直接舐めないようにするだけで充分なこともあります。
ナイロン糸やステープラーで皮膚を縫合した場合には、一般的な手術なら術後1週間から10日で抜糸ができます。退院から抜糸までの間は、特に家でしていただくことはありませんが、舐めたりしないように充分注意していただく必要があります。不妊・去勢などの手術では、術後に全力疾走で走り回ったり転げまわったりしない限り、必要以上の「安静」は必要ありません(もちろん手術の内容によって安静が必要な場合もあります。個々の手術により術後の注意事項が異なりますので、その都度詳しくご説明します)。
下の写真は、当院で行った犬の不妊手術の術創管理の様子です。当院では犬の不妊手術などの閉腹の際には、写真1のように「吸収性・モノフィラメント」を使用して連続真皮縫合を行うことが多く、皮膚の縫合はしません。開腹手術などの「テンション」がかからない部分の縫合の場合には、この方法を適応することができます。この縫合創にフィルムドレッシングを被覆したのが写真2です。フィルムドレッシングは非常に薄いため、写真ではちょっと判り難いかもしれません。この犬の場合には、エリザベスカラーはせずに、家で洋服を着せて傷を直接舐めないようにしてもらいました。特に包帯も巻いていません。

写真1

写真2
写真3は術後3日目の写真です。フィルムの下に滲み出た血液で少し茶色くなっていますが、特に問題はありません。フィルムをはがしたのが写真4です。皮膚を縫合していないため抜糸が不要で、フィルムを使用しているため「カサブタ」ができず、傷が非常にきれいにくっついているのがお分かりになると思います。

写真3

写真4
術創はフィルム材で保護されていますので、自宅で傷を消毒する必要もなく、3日経ったらフィルムを剥がして終わり、という非常に簡単な術後管理方法です。また、腹壁・皮下組織・真皮の全てを吸収糸で縫合しているため、最終的には術創内部に「糸=異物」が一切残りません。
▽注意点
消化管吻合や子宮蓄膿症、細菌性の腹膜炎など、汚染・感染を伴う手術では、上記のような閉鎖方法ができない場合があります。実際にどのような方法で縫合・閉鎖するかは手術毎に獣医師が最善と思われる方法を選択することになります。
2017.11.02(木)
皮下注射や静脈注射をする前に、注射部位の皮膚を消毒用アルコールで「ゴシゴシ」拭いてから注射をするのは、昔からどこの病院でも見慣れた光景となっています。人の病院でも、いまだに殆どの病院で「注射前のアルコール消毒」をしているのが現状です。しかしこの「皮膚のアルコール消毒」は、実は医学的には全く意味の無い行為である事が明らかになっています。
▽アルコール消毒が無意味である理由
その1)皮膚の表面をアルコールで拭いても皮膚は「無菌」にはならない。
アルコールを含め、どんなに強力な消毒薬で皮膚表面を消毒しても、皮膚は「無菌」にはなりません。たとえ皮膚の表面が一時的に「ほぼ無菌」に近い状態になったとしても、毛穴や皮脂腺の中には皮膚常在菌が生存しています。これを全て殺滅するためには、皮膚がボロボロになるくらい強力な消毒剤を使用するか、ガスバーナーで皮膚ごと焼いてしまう(!!)くらいしか方法がありません。もちろんこんなことは現実には不可能です。ですから、アルコール消毒で皮膚の表面を無菌にすることは出来ないのです。
その2)アルコール綿で拭いただけでは消毒にならない
それでもアルコールと言うのは優れた消毒薬です。しかし、アルコールの消毒効果を最も効率良く引き出すためには、アルコール綿で「サッ」と皮膚を拭いただけでは駄目なのです。アルコールで器具などを消毒する場合は「浸漬」という方法が最も効果的です。これはアルコールのプールの中に器具全体が完全に沈むようにして、10分間漬け置きする方法です。しかし皮膚にこの方法を応用することは出来ませんので、たっぷりとアルコールを染み込ませた綿花を使用して皮膚の表面を「拭く」のが一般的な方法となっています。この場合、アルコールの消毒効果が一番出るのは、アルコールが蒸発して皮膚面が乾燥する瞬間である、と言われています(それでも無菌にはなりません)。ところが、多くの病院ではアルコールが完全に乾く前に注射の針を皮膚に刺しています。でもそれで実際に「感染が起きた」と言う話は滅多に聞いた事がありません。つまり、今まで消毒していたつもりでも、実際にはきちんと消毒の効果が得られていなかったと言う事になる訳です。それでも感染が起きていないということは、「注射の前に消毒しなくても問題ない」ということがこれまでの経験から既に実証されている、ということになります。
その3)アルコール綿は意外に汚染されていることが多い
アルコールの中で生存できる細菌というのは意外に多く存在します。アルコールは医療現場で非常に多く使用されていますから、徐々にアルコールに耐性を持つようになった細菌も増えているようです。また、アルコール綿を作り置きしているような場合には、アルコールが蒸発して濃度が低下している場合もあります。特にこのようなアルコール綿の入れ物の中では、アルコールに耐性を持った細菌が繁殖している、という報告があります。汚染されたアルコール綿を注射部位の皮膚に使用することは、「何も使用しない」場合よりもずっと危険である可能性があります。常在菌は通常、その菌を保有している本人には何ら悪影響を与えませんが、外から持ち込まれた細菌は病原性を示す可能性があるからです。このような場合は、アルコール消毒は「無意味」と言うよりむしろ「有害」ということになってしまいます。
その4)皮膚の常在菌が注射針により組織内に持ち込まれても「感染」は起きない
通常の量の常在菌がそこにいるだけでは、「感染」は起きません。感染が成立するためには、組織1g中に細菌数が10万個~100万個に増殖するような生体側の問題があるか、あるいは細菌の増殖の場となる「異物」が存在する事が必要です(「感染の定義」はこちらを参考にしてください)。注射の針によって僅かな常在菌が組織内に持ち込まれたとしても、自身の白血球や免疫システムが正常に働いて、少数の細菌は直ぐに取り除かれてしまいます。従って、血行を欠いた大量の壊死組織の中に注射をするような場合を除き、健康な組織内に針を刺入して注射をする場合には、「感染」を成立させるための条件が揃わないため、感染は起き得ないのです。
実際にアメリカでは、糖尿病患者のインスリン注射はアルコール消毒などせずに、服の上から「ブスッ」と注射するのが常識となっているそうです。
その5)アルコール消毒の弊害
アルコールには非常に強い粘膜刺激性があります。アルコールが乾かないうちに注射の針を刺す事は、上記のように消毒効果が不十分になるだけではなく、針の刺入により組織に痛みを生じさせる原因となります。また、炎症や傷のある皮膚面にアルコールを使用すると非常に強い刺激性を示すため、このような皮膚には使用できません。
▽皮膚の消毒が必要と考えられるケース
上記の(その4)でも少し触れましたが、注射をする皮膚の下に大量の壊死組織や血行を欠いた組織などがある場合には、少量の常在菌でも、その中で増殖して「感染」を引き起こす可能性があるため、皮膚の消毒は充分に行う必要があります。このような場合には、アルコール消毒だけでは不十分なので、クロルヘキシジンのスクラブやポピドンヨードなどを使用して充分に消毒します。もちろんそれでも皮膚表面が完全に無菌になるわけではありません。しかし、このようなケースでは、組織内に持ち込む細菌の数を出来る限り少なくすることに意味があると考えられるため、皮膚の消毒が必要であると判断されます。
その他、皮膚の消毒が必要となるケースとしては、胸水や腹水、心嚢水(心臓と心嚢膜の間に液体が貯留すること)などの体液の貯留にたいして針を刺入する場合には、十分な皮膚の消毒が必要になります。また、関節包や脊髄内、骨髄内などに針を刺入する場合にも、皮膚を充分に消毒する事が重要になります。また関節内や体腔内にアプローチする手術の際にも、術野に持ち込む細菌数を出来る限り少なくするため、術前に皮膚の消毒を行います。
▽追加事項
消毒としては「無意味」でも、動物に注射をする際には、ときとして「アルコール」が便利な場合があります。動物の皮膚には「被毛」が密に生えているため、アルコールで毛を濡らして皮膚が直接肉眼で確認できる状態にすると、注射をしやすい場合があります。また、静脈注射の際には、アルコールで毛を除けて、血管が見えやすいようにすることで注射がしやすくなります。従って、このような目的で注射の前に「アルコール綿」を使用することがありますので、ご了承下さい。
2017.11.02(木)
手術の際には、血管を縛ったり、切開した組織や皮膚を縫合するために色々な種類の手術用「糸」を使用します。目的に合わせて、一番適切な糸を選択して使用するわけですが、実際には糸の使い方は獣医師や病院により異なります。もちろん「どのような場合にどのタイプの糸を使用するべきか」という原則はあるのですが、その常識は時代とともに変化します。
「たかが糸」と思われるかもしれませんが、手術に使用した糸の種類によっては術後の感染症、糸に対するアレルギー、異物反応による肉芽腫の形成、炎症、癒着、離開など様々なトラブルが発生する場合もあります。もちろん、たとえどのような糸を使用したとしても、生体にとって「糸」は結局のところ「異物」には違いありませんから、術後に起こるあらゆるトラブルを100%抑えることは実際にはできませんし、「糸」だけが手術の成否を分ける要因でもありません。しかし、「どの糸を使用するか」ということに、ちょっと気を使うだけで、これらのトラブルの何割かが解消されることも事実です。ここでは、一般的に手術に使用される「糸」の種類と、使用目的に応じた「糸」の使い分け、そして当院での(原則的な)「糸」の使用方法について、ごく簡単に紹介します。
《糸の種類》
◆「溶ける糸」と「溶けない糸」
手術後しばらく経って、生体に吸収されて無くなってしまうタイプの糸を「溶ける糸」=吸収糸と呼びます。「生体内の糸を分解して吸収する」というのは一種の免疫反応ですから、吸収糸を使用するとある程度の「組織反応」が見られます(組織反応があるからこそ糸が吸収されるのです)。通常この反応は軽度であり、組織内でゆっくりと進行するので、外からは判りません。
吸収糸にはカットガット*と言う「牛の腸」を原料とした天然素材の糸と、合成吸収糸とがあります。カットガット*は張力が弱く、組織内での張力の持続力が短く(早期に分解・吸収されるため)、組織反応が強く起こるため、特殊な用途以外ではあまり最近では使用されなくなりました。またカットガット*は1本ずつ滅菌されたパッケージに入っているのではなく、アルコールで満たされたカセットに入った糸をその都度必要な分だけ切って使うため、汚染される危険性も高く、したがって現在当院では使用しておりません。
合成吸収糸は、その素材の種類により多少の違いはありますが、一般的に張力が強く、組織内での張力の持続期間も数週間と長く、3ヶ月から半年くらいかけてゆっくりと吸収されます。カットガット*よりもしっかりと確実に縫合でき、組織反応も少ないため、一般的には合成吸収糸が使用されています。
これに対して、生体に吸収されないタイプの糸を「溶けない糸」=非吸収糸と呼びます。非吸収糸には「絹糸(けんし)」や「ナイロン糸」、その他の素材のものがあります。細いステンレスワイヤーなどを縫合に使用する場合もありますが、これも非吸収糸に含まれます。絹糸はその字のとおり、シルクから出来た天然素材の糸であり、生体にとっては異種蛋白なので比較的強い組織反応を示します。これに対してナイロンやポリプロピレン、ステンレスなどの合成非吸収糸は殆ど組織反応を示さないと言われています。しかし、経験的にはこれらの非吸収糸でも、異物反応を起こす個体が時として見られますが、絹糸と比較すればその危険性は非常に低いと考えられます。
*カットガットは2000年12月以降発売中止となりました。
◆「ブレード」と「モノフィラメント」
タコ糸や裁縫用の糸のように、細い繊維が何本も束になって1本の糸となっているタイプの糸を「より糸」=ブレードと呼びます。ブレードは術者にとって非常に扱い易く、しっかりと縫合・結紮が出来るという利点がありますが、細菌による汚染が生じやすく、特に絹糸は術後の縫合糸膿瘍の主な原因となっています。絹糸は、1本1本のシルク繊維が非常に細く、その繊維どうしの間隔はちょうど、「細菌」は入り込めても「白血球」は入り込めないサイズになっています。つまり、この中に細菌が入り込んでしまうと、生体の白血球は細菌を捕まえて食べることが出来ず、細菌にとっては格好の隠れ場所になってしまうのです。従って、絹糸による縫合糸膿瘍は「糸」そのものを取り除くまで、半永久的に繰り返されることになります。
これに対してモノフィラメントは、複数の糸を寄り合わせたものではなく、単一の「ツルッ」とした1本の糸で出来ています。つまりこの糸の中には「細菌が入り込む」スペースがありません。このため、細菌による汚染を起こす危険性が低く、汚染を伴う手術ではもちろんのこと、通常の手術でもできるだけモノフィラメントの縫合糸を使用することが推奨されます。

これらは何れも合成吸収糸。上の2つがモノフィラメントで、一番下のものがブレードタイプの吸収糸

こちらは非吸収糸。一番上がポリプロピレンの針付き縫合糸。真ん中がナイロン糸で、一番下が絹糸。
◆使用目的に応じた使い分け
糸の使い方も時代により変わります。昔は手術用の糸と言えば「絹糸」でした。絹糸はとても扱いやすく、丈夫であることから、血管の結紮や開腹したお腹を閉じる際の腹壁の縫合に使用されたりしていました。さすがに現在、皮膚を絹糸で縫うことはまずありませんが、腹壁を絹糸で縫合している病院はまだ時々見かけることがあります。以下に、縫合糸の「昔の常識」と「新しい常識」を箇条書きにしてご紹介します(個人の見解です)。
「昔の常識」
・ 血管や管状の臓器の結紮には絹糸を使う(滑って抜けるといけないから?)。
・ 血管の結紮に吸収糸を使ってはいけない(早めに溶けると出血するから?)。
・腹壁の縫合には非吸収糸を使う(吸収糸は強度が弱いから?)。
・腹壁は 単純結節縫合する。その際、腹膜を同時に縫合することを忘れてはならない(学生の頃は『腹膜を絶対に拾うべし』と習いましたっけ)。
・皮下(脂肪)組織は吸収糸で縫合し、最後に皮膚をナイロン糸で縫合する。
「新しい常識」
・ 血管の結紮には合成吸収糸、非吸収糸の何れを使用しても構わない。しかし絹糸はできるだけ使用しないこと。
・腹壁の縫合は合成吸収糸、非吸収糸の何れを使用しても構わない。しかし絹糸は使わないこと。
・腹壁の縫合は単純結節縫合でも連続縫合でもどちらでも良い。
・腹壁を縫合するときには、腹膜を拾うべきではない。腹筋の筋膜をしっかり縫うことが重要である。
・皮下組織は吸収糸か非吸収糸で縫合する。できるだけブレードは使用しない。
内容が少々専門的になりますが、「単純結節縫合」とは、縫合糸を1回ずつ結んでは切る方法で、時間はかかりますがしっかりと縫合することができます(と考えられています)が、結び目が沢山できます。連続縫合は組織に連続的に針・糸を通す方法で、すばやく縫合することが出来ます。腸管や膀胱など液体が漏れては困る場合の組織の縫合には、密閉性の高い連続縫合を使用します(これも、昔は単純結節縫合とされていました)。
腹壁を縫合する際に、「腹膜を拾ってはいけない」というのは、獣医師でも驚かれる方が沢山いることと思われます。私自身も学生のときには「絶対に腹膜を拾うこと」と教えられましたし、恐らく現在も学校の授業ではこう教えられているのではないでしょうか?しかし現在では、腹膜を縫合すると術後の傷に痛みを生じること、腹膜炎の発生率が上昇すること、腹腔内臓器と腹壁の癒着が起こる確率が高いこと、などが判明しており、また腹膜の再生は非常に早く縫合の必要がないこと、縫合することで却って腹膜に余計な損傷を与え、治癒を阻害していることなどが指摘されており、閉腹の際には腹膜を拾わずに、腹筋の筋膜をきちんと縫合すること(縫合糸が腹腔内に出ないようにすること)が大切である、というのが新たな常識となっています。
皮下組織を吸収糸(または非吸収糸)で縫合するのは今も昔も同じですが、脂肪織をあまり「がっちり」深く縫合し過ぎると、脂肪の虚血性壊死を起こしたりすることがあります。皮下脂肪というよりも、真皮層をしっかり縫合することが大切です。
◆当院での「糸」の使い方
以上からも判るように、糸の使い方や縫合の仕方には時代により色んな常識があります。どの時期の「常識」を取り入れたかにより、術者によって多少の違いが出てくるのはある程度仕方当然のことです。また、自分では「古い方法」であることが判っていても、「今までこの方法で問題が起きたことが無い」と言う理由で、新たな方法に変える必要性を感じない、という場合もあるでしょう。確かに、医療材メーカーから「手術用絹糸」が売られていることからも、手術に絹糸を使用すること自体は「間違い」ではないのですが、生体に残る部分にはなるべく使用しないなど、使用方法には気を配る必要があると思われます。
当院では、
「縫合糸による汚染・感染を防ぐこと」
「縫合により不要な損傷を組織に与えないこと」
「縫合により組織の修復をできるだけ妨げないこと」
「生体内にできるだけ異物を残さないこと」
などを目的として、縫合糸の使用方法について、原則的に以下のように考えています。
・血管などの結紮には合成吸収糸、または非吸収性のモノフィラメントを使用する。
・原則的に絹糸は使用しない(腫瘍などの「取り除く部分」には使用することがあります)。
・腹壁は合成吸収糸による連続縫合 で、腹筋筋膜をしっかりと縫合する。
実際の手術では、その場その場で「最も適切」と思われる縫合糸や縫合方法を選択することになりますので、場合によっては必ずしも、この使用原則に従うことができないケースもあるかもしれません。しかしながら、通常の手術では殆ど全ての場合、この原則に従って縫合糸を選択しています。
2017.11.02(木)
▽「抗生物質」とは?
抗生物質という言葉は、皆さんも良く耳にされることと思いますが、実際にどんな薬のことを言うのか、ご存知でしょうか?「抗生物質」とは、読んで字のごとく「抗‐生物‐質」、つまり生物(主に細菌)に対抗するための薬のことで、種類により細菌を死滅させてしまうものや、増殖を止めるだけのものなどがあります。俗に「化膿止め」などと称して処方されることもありますが、体内や体表の細菌の繁殖を抑えたり、細菌自体を破壊したりして、感染から体を守るために投与される薬です。
▽手術時の「抗生物質投与」について
私達を取り巻く環境中には、眼に見えない細菌やカビが溢れています。私達人間を含めて、あらゆる動物の皮膚や腸の中にも「常在菌」と呼ばれる細菌が生活しています。手術の際に、全身麻酔をかけることにより体温や恒常性が低下して、抵抗力が低下すると、普段は何ら悪さを働かないこれらの細菌達が増殖し、手術部位 の感染(化膿)が起こる、と考えられています。これを防ぐため、手術の際には抗生物質を、予防的に投与することが推奨されて来ました。 しかしこの考え方は最近変わりつつあります。
▽「薬剤耐性菌」について
抗生物質には多くの種類があり、それぞれに作用のし方や「効く細菌の種類」が異なります。目的とする細菌の種類によって、使用する抗生物質の種類も少しづつ違うのです。ところが、今まである細菌に対し「効いた」はずの抗生物質が、次第に効かなくなってしまうことがあります。これは、細菌が、その抗生物質に対し、「抵抗力=耐性」を持ってしまったためです。このような細菌を、「薬剤耐性菌」と呼びます。「薬剤耐性菌」は、正常な免疫力をもったヒトや動物には殆ど無害ですが、老齢や病気、免疫抑制剤を投与している場合など、免疫が低下しているヒトや動物にとっては大きな脅威となります。特に人間の病院では「MRSA」の院内感染などが大きな問題となっています。
▽「耐性菌」を増やさないために
このため、「耐性菌」を増やさないことは、公衆衛生的にも非常に大切なことです。「耐性菌」を増やさないためには、「不必要な抗生物質の使用を避ける」ということが重要です。1999年に「アメリカ疾病予防局(CDC)」より出された「手術部位 感染の予防に関するガイドライン」では、「抗生物質は手術中適切な血中濃度を維持する様に投与し、術後に予防的投与を延長しないこと」としています。またこの報告では、抗生物質の「予防的投与」と術後の汚染による「感染予防」の間には関連性がない、ともしており、通常の手術では術後抗生物質を予防的に投与する必要がないことを説いています。また最近では「米国獣医学会」でも、不要な抗生剤の使用を避けるよう呼びかけています。
そもそも「抗生物質」は感染の「治療薬」であり、決して「予防薬」ではありません。しかしながら実際には「抗生物質を投与せずに感染が起きたらどうしよう」という不安感を払拭するだけの目的で、不必要な抗生物質の投与が頻繁に行われているのが現状です。つまり、人間が自らの手で薬剤耐性菌を作り出し、今度はその耐性菌に自分たちが苦しめられ、さらに強力な抗生物質を開発して乱用する、という悪循環に陥ってしまうのです。今回のCDCのガイドラインは、この悪循環に一定の歯止めをかけるのに役立つことと思われますが、私たち一人ひとりが意識して事態を改善して行こうとしない限りこの状況はなかなか変わらないでしょう。
▽当院での「手術の際の抗生物質投与」の方針
これら最近の動向を踏まえ、当院では、
1)術前および術中の適切な抗生物質の投与
2)清潔な手術操作
3)感染を起こし難い手術材料(縫合糸など)の使用
4)患者間感染の防止
などの徹底により不要な抗生物質の使用を最小限にするよう心掛けています。著しい汚染や感染を伴わない手術(例;不妊手術や去勢手術など)の際には、原則として退院時に抗生物質を処方しておりません。今まで「手術後は抜糸まで抗生物質を投与する」のが「常識」と考えていた方は、「本当に大丈夫?」と心配されるかもしれません。しかし、「常識」は時代と共に変わるものです。皆様のご理解とご協力を、宜しくお願いいたします。
▽補足と注意点
手術の性質によっては手術前日〜数日前から抗生物質の投与をお願いする場合があります。また、術前・術後の投与法に関しては、獣医師の指示に従ってください。このガイドラインは「予防的投与」に関するものであり、皮膚病やその他、感染症に対する「治療的投与」に於いてはこの限りではありません。
2017.11.02(木)
「創傷治療」の「傷を消毒してはいけない」にも書いた通り、「傷を消毒する」ことは医学的に無意味であるだけではなく、傷の治癒を遅らせ、患者に苦痛を与え、時としてアレルギーなどのショックを引き起こしたり、白血球やマクロファージなどの免疫細胞を死滅させることで却って感染を助長させる可能性もあるということが判っています。つまり「傷を消毒する」ということは、「治療」の名を借りた一種の傷害行為であると言うのが最近の考え方です。

しかしながら、人間の病院を含めて多くの病院ではいまだに「傷の消毒」が日常的に行われています。最新の医学的知見では「間違いである」ことが判明しているにも関わらず、何故いまだにこのような行為が行われているのでしょうか?
「過去100年以上続けられてきた常識的治療」を、いまさら覆すというのはなかなか難しいことなのかもしれません。実際には、多くの傷;特にかすり傷などの小さな傷は、たとえ消毒してもすぐに治ってしまいます。これは「消毒をして傷が治るのを邪魔したのにも関わらず、強い治癒力で傷が自ら修復した」と考えるのが正しいのですが、一般的には「きちんと消毒したから治った」と捉えられてしまいます。放っておいても勝手に治ってしまうような傷の場合は、少々消毒したくらいでは然程悪影響を受けずに治癒する能力を持っているのです(だからと言って消毒しても良い、という訳ではありませんが…)。
しかし中には、非常に治癒が悪く、なかなか治らない傷というのも存在します。治らない原因はそれぞれの傷により様々ですが、このような「治り難い」デリケートな傷を治療する場合には、絶対に消毒してはいけません。ただでさえ傷の治癒を邪魔する因子が幾つもあるのですから、さらに消毒で追い討ちをかけるようなことをすれば、傷は治らないばかりか却って大きく広がって余計に悪化してしまう場合もあります。
したがって、当院では「傷を消毒する」行為は一切行っておりません。
また、「傷の治療」に関する相談や「治らない傷」の紹介なども、随時受け付けております。お電話かメールでお問い合わせください。