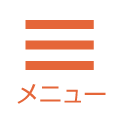ブログ・コラム
Blog2005.12.01(木)
数年前のことになりますが、私の勤務していた病院に、ある犬の飼い主の方から質問の電話がかかって来ました。お話を伺ってみると、その方の犬が何とか言う「お茶」を葉っぱごと一袋全部食べてしまい、その後痙攣などの神経症状を起こして亡くなってしまった、と言うことでした。人間が普段、何の問題も無く(むしろ健康に良い、と思って)飲んでいる「お茶」を食べたことが原因で、本当にこのようなことが起こるのでしょうか?というのがそのときの質問でした。お茶にも色々な種類があり、私自身もそれらひとつひとつのお茶の成分やその含有量などに関して詳しいわけではありませんが、一般的な回答として以下のように答えた記憶がありあます。
「大抵のお茶と言うのは普通、カフェインやテオブロミンなどの成分が含まれていますし、ハーブティなどにはそれ以外にも様々な薬用成分が含まれていることが知られています。それぞれのお茶に適した方法で飲用に供する場合には、これらの成分が毒性を示すことは殆どありませんが、『お茶の葉をそのまま食べてしまう』とか、『煮出してはいけないお茶を煮出して飲む』とか、指定された用法以外の方法で摂取した場合には、有害な作用を示す可能性を否定することは出来ません。しかも人間に比べて、犬のほうがカフェインなどに対する感受性は高いと考えられますので、何十杯分ものお茶の葉を大量に食べてしまったと言う場合には、これらの物質による中毒を起こして、場合によっては死亡してしまうことも考えられないことではありません。」
電話による質問でしたので確定的なことは言えませんが、お茶に含まれる成分による中毒の可能性は充分あると思われました。このように、一般的には安全(あるいは体によい)と思われているものでも、摂取の方法や量、あるいは摂取する動物の感受性によっては危険なこともあります。「毒物・中毒物質」と言うと、医薬品や家庭内の洗剤類、殺虫剤や除草剤、タバコやアルコール類などを直ぐに思い浮かべるのが普通だと思いますが、今回はこのような「明らかに危険なもの」ではなく、一見すると安全そうなものの中から中毒を起こす可能性のある「意外なもの」を幾つか紹介したいと思います。
アメリカのASPCA Animal Poison Control Center(動物の中毒管理センター)は、2003年4月から2004年4月までの間に「ブドウおよびレーズン」を摂取したと言う犬の報告を140例受けており、そのうち50例では嘔吐や腎不全などの症状を示し、うち7例が死亡したと報告しています。実際にはブドウ・レーズンに含まれる何と言う成分が、犬に対して毒性(主に腎毒性)を示しているのか、と言うことは判っていませんが、現段階では犬に対してブドウやレーズンを与えることは避けるべきである、と警告しています。
また同様に Animal Poison Control Centerによって報告されたマカダミア・ナッツに関連した中毒は、1987年から2001年までの間に48件あったそうです。人では、マカダミア・ナッツによるアレルギー・ショックが報告されているそうですが、犬の場合の症状は嘔吐や虚脱、沈うつ、運動失調、高体温などで、人の場合の症状とは異なっています。この場合も、本当の原因物質はまだ特定されていませんが、やはり犬にマカダミア・ナッツを与えるのはやめたほうが良いでしょう。(→マカダミア・ナッツ中毒pdf.)
漢方薬や生薬などは「副作用が無く安全」などと考えがちですが、実は必ずしもそうではありません。例えば、マオウ(麻黄)と言うのは気管支拡張剤であるエフェドリンの原料で、漢方薬などには普通に含まれている成分ですが、多量に摂取すると興奮、痙攣、幻覚、心拍・血圧上昇などの症状を引き起こすことが知られています。また朝鮮人参に含まれるサポニンと言う成分には、血糖値やコレステロール値を下げたり、血圧や造血作用を刺激する働きがあると考えられていますが、かなり大量に摂取した場合には中毒を起こす可能性があると考えられています。(→マオウの危険性に関してはこちらpdf.)
普段何気なく庭先や部屋などに飾っている観葉植物の中には、食べると非常に危険な毒物を含んでいるものが沢山あります。これからクリスマスの時期になると良く見掛けるようになるのがポインセチアです。あの緑と赤のコントラストがまさに「クリスマス」の雰囲気を醸し出すので、非常に人気のある観葉植物です。ポインセチアは、以前考えられていたほどには強力な毒性は持たない、と言うことが最近の研究で判ってきたようですが、一株まるまる食べてしまうようなケースでは、下痢や嘔吐、咽喉頭や食道の炎症を引き起こす可能性があります。また小型犬や子犬などでは、少量でも中毒を起こす可能性は否定できませんので、充分注意する必要があるでしょう。クロガネモチはナンテンに似た赤い実をつける植物で、英語ではHollyなどとも呼ばれ、やはりクリスマスの時期に良く見掛ける植物のひとつですが、この実と葉にはイリシンと呼ばれる物質の他、カフェインやテオブロミンなどの成分が含まれており、大量に摂取した場合には中毒を引き起こします。
このように、私たちが普段何気なく食べたり、飲んだり、身の回りに飾ったりしている「一見何の危険性もなさそう」なものが、犬や猫たちにとっては危険を及ぼす可能性のある物質であることも珍しくありません。思わぬ事故を起こさないように充分注意して、小さな命を守ってあげてください。
2005.08.06(土)
■ 「生食」とは何か?
「生食」、一般的には「なましょく」と呼ばれているようです。様々な人がそれぞれの解釈で「手作りフード」や「無添加フード」と称する食餌を独自に(?)編み出しているのが現状ですが、ここで定義する「生食」とは特に、BARF dietに代表される「生の骨や肉、内臓に野菜などを足して与える」という方法を指すことにします。BARFとは、Biologically Appropriate Row Foodの略と言うことですが、90年代初めにオーストラリアのとある獣医師が提唱した食餌法だそうです。「犬の家畜化」の過程において、約1万年前から犬は人の集団が排出する「ゴミ」を摂取するようになり、人の食べ残しやゴミ、排泄物を食べる生活を開始したそうです。この時点での犬の食餌を原点とし、この食餌内容に最も近い成分になるように、生の骨や肉、内臓などを適量に調整して与えるのが「最適の食餌である」とするのが所謂「生食」dietと言う訳です。
■ 「最適の食餌」の根拠は?
ここでまず疑問なのは、「犬にとって最適な食餌」が何故「1万年前の人の食べ残し」なのかと言うことです。そこから「犬の家畜化」が始まったから、と言うのは一見納得できそうな理屈ですが、「犬」と言う動物自体の歴史は1万年前から始まったわけではありません。それ以前の何十万~何百万年も前から少しずつ進化し続けて来たのです。たまたま1万年~1万5千年前に、人の集団に近づいて生活するという一群が現れました。人の集団と共に生活することは双方にメリットをもたらした訳ですが、特に犬にとってのメリットは「食料の安定供給」が得られると言うことでしょう。狩猟をしなくても「ゴミ捨て場」を漁れば食料にありつくことができるのです。肉食動物にとって「狩猟」と言うのは非常に不確実でリスクの高い摂食方法です。数日間も食餌にありつけないこともあります。狩猟で自分たちが怪我をしたり命を落とすこともあります。餓死することもあります。このようなリスクを冒すよりは、とりあえず安定して食料を得ることが出来る「人間との生活」を選択するのは「生存する」うえでは賢い選択でしょう。しかしこの食餌が「犬にとって最適」かどうかは判りません。効率よく生存するために仕方なく選択した生活様式で得られる食餌が何故「最適」なのか?何故それ以前でも以後でもなく、「1万年前の人の食べ残し」が最適なのか?根拠がまるで不明なのです。あたかも「犬は人の食べ残しを食べるために生まれて来た動物である」と言うような、西洋的(?)な人間中心の発想が根底にあるような気がしてなりません。
■ 「加熱調理」は問題か?
生食を推奨するもうひとつの理由として「犬はもともと加熱調理した食餌を食べる能力が低い」という意見が挙げられているようです。これは特に科学的根拠がある訳ではないのですが、「当たり前」と言えば「当たり前」…犬が自分達で捕まえた獲物を捌いて加熱調理するわけがありません。しかしそれを言えば、人だって肉や野菜を加熱調理して食べるようになったのはこの数万~数十万年のことで、火を使うようになる前は「生食」だったのです。それならヒトだって加熱調理したものを食べないほうがよい、という理屈になります。現在、肉や魚などを「生」で食べる習慣を持つ国は、世界でも日本をはじめほんの一部の国だけです。しかも「主な蛋白源」として、毎日牛刺しや馬刺しを食べているわけではありません。確かに生で食べることのメリットもあるのでしょうが、本来は動物の肉や内臓を「生で食べる」と言うことは非常にリスクを伴うことです。生のほうが消化に悪いものもありますし、様々な寄生虫やウイルスなどの病原体に感染する可能性も決して低くはありません。このようなリスクを回避し、より安全に効率よく食餌をする為の方法として「加熱処理」が極めて有効なのは周知の事実です。
■ 「自然・野生」に対する幻想
人や犬・猫を含めて、元々「野生」で生活していた頃の食餌が生物学的に最適なものである、というのは一見理に適った考え方です。しかしこのような考え方の根底には、「地球」とか「自然」と言うものに対する「甘い幻想」が流れているように思います。実際には「自然」とは厳しく辛いものです。地球は決して人や動物に対して甘くも優しくもありません。自然は常に生物に試練を与え、絶滅に追いやろうとする生物学的圧力を与えます。この圧力が原動力となって生物が進化するわけですが、進化とはつまり「弱肉強食・適者生存」そのもののことです。決して「最適」ではない環境の中でも、何とか(他者を排除してまで)蔓延り、生き残って来たのが私たちを含めて現在地球上に生存する生物です。残念ながら、野生動物が仲良くのんびり幸せに生活している、というのは漫画やおとぎ話の世界の出来事でしかないのです。
植物・動物に限らず、他者を「食べる」と言うこと無しに、われわれ動物は生存することが出来ません。しかしこの「他者を食べる」と言う行為には、必ずリスクが伴います。多くの植物には毒物が含まれていますし、動物を食べることで寄生虫や感染症やアレルギーを起こす可能性もあります。発癌性物質や中毒物質として多くの天然の物質が知られています。100%安全な食物は地球上に存在しません。しかしこれらの食物の持つ「毒性」や「危険性」をなるべく希釈し、拡散し、リスクを分散(例えば品種改良したり、毒性の少ない品種を選別したり、調理・加工したり、1種類のものだけを食べるのではなく色々なものを少しずつ食べるようにする、など)させて私たちは現在の比較的安全な食餌を選択しているわけです。
■ 「ペットの食餌」流行の変遷
一昔前までは、犬や猫に「ペットフード」を与えると言うのはそれ程一般的ではありませんでした。日本には「猫まんま」と言う言葉がありますが、昔は人の食べ残したご飯に味噌汁をかけただけのものを犬や猫に与えていたのです。こんな「低蛋白」の食餌では当然犬や猫の栄養要求を満たすはずがありませんが、おそらくこの時代、犬や猫たちは屋外で自由に蛙やネズミなどの小動物を捕まえて食べたり、それこそ「ゴミ・残飯」をあさったりして何とか生き延びていたのでしょう。このような時代を経過し、やがて「ペットフード」と言うものが開発されました。当初のペットフードは「栄養学」などという発想は殆ど無かったはずなので、現在のフードに比較するとかなり粗悪なものだったのでしょう。色々な栄養素の欠乏症を引き起こしたりすることも稀ではありませんでした。やがてアメリカのHill’sという会社が、専門家の獣医師による研究成果を取り入れながら、動物の栄養学という分野を確立し、これを基に栄養的に優れたペットフードを開発するに至りました。その後、色々なメーカーが「栄養学」を基に沢山の種類のペットフードを作るようになったのは誰もがご存知のことでしょう。
そして現在は、これらの「ペットフード」にも「原材料」とか「添加物・保存料」などに関して問題がある、という意見を持つ人たちが増えてきており、より安全で「自然」なフードを与えたいと言うことで、「無添加フード」や「ナチュラル・フード」などと称する(これらの言葉には定義がないので、詳細な意味は不明です)ペットフードが多く出回るようになりました。さらにその中でも、より強い「拘り」をもつ人たちは、「ペットフードなど体に良いわけが無い、生の肉・骨・内臓などを与えるのが自然本来の食餌なので体に良い」という考えを持つに至り、「生食」が(一部で)熱心な「信者」を獲得するようになったようです。
■ ドライフード(ペットフード)は悪者か?
では、ドライフードなどを中心とする所謂「ペットフード」は本当に「体に悪い」のでしょうか?実はこの答えはそう簡単には出るものではありません。但し、はっきり言えることは、野生の状態で生活している動物や、「ペットフード」以前の「猫まんま」に近い食餌をしている動物に比較して、ペットフード中心の食生活をしている動物の寿命は確実に長くなっている、と言うことです。これは当然、食餌以外の要因も沢山あるのですが、少なくとも「野生・野良」状態の食餌や生活環境が動物にとって(個体が健康で長生きする、と言う意味に於いて)決して最適なものであるとは限らない、と言うことが言えるのではないでしょうか?
もちろん現在のペットフードが「完璧」なものであるとは思いませんし、いろいろな問題を抱えているのは事実です。しかし、ここ数年の犬・猫の寿命の延長や栄養関連の疾患の減少など、動物たちが長く健康に生きるようになった状況を生み出すうえで、ペットフードが果たしている役割は多大なものがあると言うことは現実として認識しなければなりません。
「ペットの病気は増えているのではないか?」と思われる方もいることでしょう。しかしこれは一概には言えません。昔は栄養性疾患や寄生虫病、感染症などの、どちらかと言えば「単純」で「重大」な病気が多かったのですが、近代では内分泌疾患やアレルギーなどの免疫疾患、高齢に伴う腫瘍性疾患など複雑な病気が増えています。これは人間でも同様のことで、医学が発達すると遺伝性疾患が増えるというジレンマはどうしても避けることが出来ませんし、寿命の延長に伴って高齢疾患が増えるのも、ある意味では当然のことと言えるでしょう。これを「食餌のせいだ」「ペットフードのせいだ」と言うのは一見分かりやすいのですが、科学的・統計学的に証明されている訳ではありません。
■ 「食品添加物」は危険なのか?
人の食物を含めて、多くの食品には保存料などの「食品添加物」が含まれています。食品添加物そのものは、もちろん「体に良い」物ではありません。しかし、
「食品添加物が入っている」=「体に悪い」
「無添加」=「体に良い」
という単純な発想は、かえって危険なこともあります。
日本の環境問題は、高度成長時代の60~70年代が最悪の状態でした。最近問題になっている「石綿」なども、この時代に最も頻繁に使用されていました。これは食品に関しても同様で、この時代には様々な保存料や合成着色料などが、それ程の規制もないままに使用されていました。これにはある程度の理由があって、それ以前の時代は人々はほぼ「自給自足」に近い形の食糧供給をしていたのですが、高度成長に伴って人口が増加し、反対に食料自給率は低下しますので、それ以前のような「必要な分だけ作って、余った分は腐るに任せるか肥料にする」と言うような原始的な食糧供給形態ではとても足りなくなってしまったのです。そのため、出来るだけ多めに農作物を作って保存・加工することで供給量を賄い、余って腐らせてしまう食料を出来るだけ減らす、という必要が出てきます。このために保存料や防腐剤は必要不可欠であり、安定した食糧供給のためには欠かせないものとなったのです。また保存料には、食品の腐敗による食中毒やカビによる健康被害、虫食いなどを防ぐ効果もありました。
高度成長の時代が終わって生活が豊かになり、健康や食品の安全、という分野まで意識するような余裕が出てくると、当然ながら「添加物は危険なのではないか?」と言う発想が出てきます。そして保存料や防腐剤、農薬に関する見直しや規制が年々厳しくなり、現在ではかなり安全性の確立したものだけが使用されるようになっています。2005年現在、30年前に比較して食品を取り巻く環境はかなり改善されています。保存料を使わずに、古くなったり酸化したり、カビが生えたものを口にするくらいなら、安全性試験に基いた適正な保存料の添加された食品を摂取するほうが遥かに安全です(カビ毒の発癌性はどんな化学物質にも勝ると言われます)。
これは人の食品に関する話ですが、ペットフードの場合は人の食品のような明確な「法規制」が無いため、「何でもあり」と言う状況であることは否めません。そしてこれは、各メーカーが公表しているデータを信用するしかないわけです。小さくて名前も聞いたことが無いようなメーカーのものはやはりあまり信頼度が高いとは思えません。大きくて名前の通った企業なら無条件で信頼できるか?と言えばそうとも限りませんが、最低限AAFCOの基準を満たしているもので、獣医栄養学の専門家が開発に携わっているような、獣医療と動物の健康に貢献してきた実績のあるメーカーと言うことなら一定の信頼がおけると、個人的には思っています。「添加物は一切入っていない」と言う謳い文句は信憑性に欠ける(もし本当なら「短期間で腐るのではないか?」という心配がある)ものですが、「添加物として何がどれだけ入っているか」と言うことが判っていれば、その方が却って「安全性が保障されている」ということになるのではないでしょうか。
■ 「手作り食」でAAFCOの定める栄養要求を満たすことが出来るか?
この答えはYesでもありNoでもあります。物理的には可能でしょう。様々な食材を集め、栄養成分をチェックし、全ての項目において必要量を満たすように計算したうえで、全体のカロリーを適切に調節する。足りない栄養素は添加物として調節する。当然ながら特定の成分が過剰にならないように注意する必要がありますが、そのためにカロリーまで減らしてはならないので、何かを減らしたら他の成分を増やさなければならなくなります。これはなかなか複雑な「パズル」です。犬や猫を飼っている方の多くが1日24時間のうち、その殆どの時間を「ペットフード作り」に割くことが出来るような優雅な生活をしている方ばかりではないでしょうし、栄養学の専門的な知識を持った人ばかりでもないでしょうから、「適切な、正しい手作り食」を作るために生活のほぼ全てを犠牲にするのはあまり賢い考え方ではないように思われます。また、せっかく長い時間をかけて出来上がった手作り食が、よく調べてみたらバランスの悪いものだった、と言うことも珍しくありません。100%の手作り食で上手に栄養管理が出来る人と言うのは、恐らく一般の飼い主の方の中の、1割程度もいないのではないでしょうか?
栄養学の専門家でさえ、長年かけて研究・開発して得られた「バランス・フード」の栄養配合を、私たちのような栄養学の素人が一朝一夕にうまく作ることが出来る、と考えるほうが無理があるのではないでしょうか?つまりこの問題は、必ずしも「不可能」ではないけれど、失敗するリスクが非常に高い、ということだと思います。
■ 「環境問題」をどう考えるのか?
ペットフードの問題を考える際に、環境問題なんか考える必要があるのか?と思われることでしょう。確かに蛇足かも知れません。どうでも良いこと、かも知れません。しかしこの「生食ブーム」「自然食ブーム」という流れの中には、人の食品事情における「無農薬・有機野菜ブーム」「自然食品ブーム」と同じ発想が、根底にあるような気がしてならないのです。「自然」が安全とは限らない、と先に書きましたが、同様に「無農薬野菜」「有機野菜」が「普通の野菜」よりも安全で健康によい、という科学的根拠はありません。もちろん輸入品などで、規制対象となっている農薬を使用している場合などは「危ない」のが当たり前ですが、これは「普通の野菜」と言う範疇には入れないのが当然でしょう。決められた農薬を決められた方法で使用している限りにおいては、かなり安全と言うことができます。それでも所謂「有機野菜」を有難がると言うことは、これらの食品は一種の「贅沢品・嗜好品」と捉えることが出来ます。無農薬野菜・有機野菜を作るためには、通常の野菜を育てるよりも多くの費用・労力;つまり多くのエネルギーが必要です。有機野菜を育てるための有機肥料も、河川などに流れ込んで環境汚染を起こすこともあります。やはり「贅沢品」を使用することは環境負荷が大きい、ということです。もしも私たち人間の食べるもの全てが生の野菜、肉、魚などで、一切加工品を使用しないとしたらどうでしょう?スーパーに並んでいる食品全てが「無農薬・有機野菜とそれらで育てた家畜の肉」だとしたらどうなるのでしょう?日持ちがせずに余った食品は全て腐ってしまい、廃棄することになります。天候や害虫被害などによる作物の不足はすぐさま食糧不足を引き起こします。不足を補うために、より多くの土地を農地として開墾する必要が出てくるかもしれません。意外に思われるかもしれませんが「農地」と言うのは立派な環境破壊です。「地球に優しい」というフレーズと「自分たちの体に優しい」ということは、同じ「エコロジー」と言う言葉で括られてしまう傾向がありますが、実は、原則的に「相反する」ものであると言うことを理解しなければなりません。私たちが「それなりに」安全な食生活をしながら、「それなりに」環境の汚染を防いで生存してゆくためには、環境負荷の大きい「贅沢品」を追い求めるのではなく、効率の良い、無駄なエネルギーロスの少ない生活、と言うのも少しは考えて行かなくてはなりません。
私たち人間が「環境負荷」の大きい「自然食品」を追い求め、さらに犬や猫にまでこのような食材を日常的に与えるとなると、一体どのようなことになるのでしょうか?現在日本国内の犬・猫の飼育頭数はそれぞれ1000万頭を越えています。これら皆が「自然食品」を使った「生食」を始めたとしたら、一体どれだけのエネルギーが余計に消費されることになるのか?ちょっと気になるところではあります。
■ ではどのような食餌を与えたらよいのか?
最適な食餌は何か?と言う疑問に対する明確な答えは結局のところありません。コアラにとってはユーカリの葉が最適であることは疑いようがありませんが、犬や猫などの動物は、限られた環境でただ1種類の食物だけを食べて生きてゆくようには進化していません。繰り返しますが、100%安全な食物は、地球上には存在しません。私たちが一生のうちに摂取する発癌性物質の多くは、保存料や添加物に含まれるものではなく、野菜などの食材に元々含まれている成分であると言うことが知られています。どんな食物でも、アレルギーを起こすリスクはゼロではありません。ある「自然食品」関連のサイトで目にしたのですが、「アレルギーの多くは蛋白質が原因なので、パイナップルやパパイヤに含まれる蛋白分解酵素を一緒に摂取するとアレルギーが起きない」と言う意見は、「酵素」自体が立派な蛋白質であると言うことを忘れています。医薬品でも、酵素剤はアナフィラキシーを含む激しいアレルギーを起こす可能性があるので、注意する必要があると言うのが一般常識です。
比較的安全な食生活を送るために大切なことは、「拘りを持たない」と言うことです。何かひとつの食材やサプリメント、栄養剤に拘って、毎日同じものを摂取すると言うのは、リスクの分散と言う意味からしても、アレルギーの発現ということを考えても、決して安全性が高いとは言えません。例えば、ビタミン欠乏症でもないのに毎日ビタミン剤を摂取するのは危険なこともあります。食糧不足の時代ならいざ知らず、飽食のこの時代に、小学生に肝油ドロップを毎日与えることが「安全」とは考え難いのではないでしょうか?もちろん全ての食物が「毎日摂取したら危ない」と言う極端なことを言っているわけではありません。日本人は「ご飯」と「味噌汁」を毎日摂取しても安全なことは、歴史が証明していますし、主食となるようなものは比較的安全だと考えても大丈夫でしょう。ペットフードだって、それなりに信用のおけるメーカーのフードなら、長期間与えても安全なことは給与試験が証明していますので、その範囲では「問題ない」と考えられます。1種類のフードだけでは心配、ということなら、幾つかのメーカーのものや、異なる種類のフードを時々ローテーションで入れ替えながら与えても良いでしょう。その方が「リスクの分散」が出来るかもしれません。現に私の場合、自分の家の犬には幾つかの種類のフードを、その時々で替えながら与えています。時には加熱調理し肉や野菜を少量与えることもありますが、日常的には与えていません。つまり「これと言った拘りを持たない」と言うのが拘り、と言うことです。
もちろん、特定の疾患などを持っていて、療法食による食事管理が必要な動物の場合は、「色々なフードをローテーションで与える」ことにより病気が悪化する可能性がありますから、決められた療法食を与え続ける方が「リスクが少ない」と考えられます。
■ まとめ
私は、「生食」や「自然食品」(実はこれは定義が曖昧)が「危ないからいけない」といっている訳ではなく、ペットフードが100%安全である、と言っている訳でもありません。しかし同時に、ペットフードが体に悪くて「生食」が絶対に安全、と言う考えにも少なからず疑問を持っています。「地球温暖化」ではないですが、現代の文明的生活に警鐘を鳴らすこと自体は良いのですが、変に終末思想を煽るような言文が世界的に流行しているような気がします。食物の「自然回帰」と言うようなこれらの風潮も、その流れのひとつのような気がしています。あまり極端な意見に惑わされず、現実的に、合理的に情報の信憑性・正確性を判断することが大切なのだと思います。答えが出ないときには、態度を保留することも決して間違いではないでしょう。
2005.07.09(土)
以前の病院に勤めていたときのことですが、ある小型犬の飼い主さんが暫くぶりに来院し、「実は入院して腎移植を受けたんです」という話を聞いて、びっくりした事があります。何故そんなにびっくりしたのかといえば、その飼い主は私よりも一回り近く年下の、まだ二十歳を少し越えたばかりの若い女性の方だったからです。そのような若い年齢で、腎不全を患い腎移植手術という大手術を受けるなどということは、私自身には想像もできないような大変なことに思えたのです。臓器移植というのは、手術が成功すればそれで終わり、というものではありません。ドナー(臓器提供者)から移植された臓器は、レシピエント(臓器をもらう人)の体から見れば「異物」とみなされてしまう為、本人の免疫系が働いて移植臓器を攻撃してしまうのです。これがいわゆる「拒絶反応」というもので、拒絶反応が起きるとせっかく移植した臓器が死んでしまうため、レシピエントの人は自分自身の免疫反応を抑えるために、免疫抑制剤を飲み続けなければならないのです。ところがこの免疫抑制剤は、移植臓器の拒絶反応を抑えるだけではなく、ウイルスや細菌、寄生虫などの病原体に対する抵抗力も同時に低下させてしまうため、感染症に対する予防には非常に神経を使う必要があるのです。
私達がペットとして飼育している犬や猫その他の動物から、人に移る病気(人畜共通感染症)が幾つかあることが知られています。健康な人にとってはそれ程の被害とはならなくても、何らかの理由により免疫状態が低下しているような人にとっては、非常に大きな危険をもたらす可能性があります。そして当然のごとく、この女性の場合も主治医から「犬を飼うのはやめたほうが良い」と言われたそうです。
免疫機能が低下するのはなにも「臓器移植」の場合だけではありません。日本でもHIV患者の方の数は増加していますし、その他の慢性疾患や加齢などによっても免疫が低下します。寝たきりのお年寄りのいる家庭もあるでしょうし、乳幼児や妊婦の方なども非常にリスクが高いと考えられます。ではこのような人達は動物を飼わない方が良いのでしょうか?
アメリカのCDC(疾病対策予防センター)は、HIV患者の為の「ペット飼育ガイド」を出しています。そのガイドの1行目には「(HIVに感染していても)ペットを飼うことをあきらめる必要はありません」とあります。そしてその後には「ペットから病気を移される可能性はありますが、そのリスクは低いものです」、「(感染を防ぐためには)幾つかの基本的な注意点を守るだけで充分です」と続きます。
具体的な注意点としては、以下のようなものを挙げています。
・ 動物に触ったり遊んだりした後は(特に食事の前には)よく手を洗うこと。
・ ペットにはペットフードだけを与えるか、肉を与える場合はよく加熱調理したものを与えること。加熱不足の肉を与えたり、トイレの水や生ゴミ、他の動物の糞などを食べさせないように注意すること(下痢をしたり寄生虫などに感染する可能性が高い)。
・ 下痢をしている動物には触らないこと。1~2日以上下痢が治らない場合は、HIVに感染していない人に頼んで動物病院に連れて行ってもらうこと。
・ 病気の動物や、生まれて6ヶ月に満たない小さな動物(特に下痢をしている動物)を家に連れて来ないこと。動物を飼う前には動物病院で健康チェックをしてもらうこと。
・ 色んな病気を持っていることが多いので、野良犬、野良猫などには触らないこと。
・ 動物の便には絶対触らないこと。
・ 猫のトイレの掃除をする時には、HIVに感染していない(妊娠していない)誰か他の人に頼むか、自分でするときはビニール手袋をはめ、終わったらすぐに石鹸で手をよく洗うこと。
・ 猫の爪はきちんと切っておくこと。もし引っ掻かれたら直ぐに石鹸と水でよく洗うこと。
・ 口や傷口などをペットに舐めさせないこと。
・ ペットとキスをしないこと。
・ ノミの駆除・対策をしっかりすること(ノミは様々な病気を運んで来るため)
・ 爬虫類は飼わないこと。もし爬虫類に触ったら、すぐに石鹸と水で手を洗うこと。
・ 水槽やペットのケージの掃除をするときはビニール手袋をはめ、終わったら直ぐ手を洗うこと。
・ 猿やフェレットなどのエキゾチックペット、アライグマやライオン、コウモリ、スカンクなどの野生動物を飼わないこと。
注意》上記の項目は私が一部を簡略的に日本語に訳したものですので、詳しい内容に付いてはCDCのサイトでご確認ください。
これはHIV患者のためのガイドですが、臓器移植患者の場合もほぼ同様な注意さえ守れば、安全にペットと暮らすことができるということです。つまり健康に何の問題も無い、6ヶ月齢以上の(出来れば野良ではない)犬や猫を飼育する分には殆ど危険性はない、と言って良いと考えられます。そして特に免疫状態の低下している人の場合は、具合の悪い動物(特に下痢をしている動物)には触らず、便の始末は他の人に頼むこと、動物が食べる物に気をつけることが重要です。そしてワクチンを接種やノミの駆除、定期的な駆虫を行い動物の体をクリーンで健康に保つことで、自分自身の健康を守ることができると言うことになります。
テレビや新聞などで時折、人畜共通感染症の「怖さ」ばかりを煽って「ペットブームに警鐘を鳴らす」と言う趣旨の報道を見ることがあります。確かに人畜共通感染症の怖さは知っておかなくてはなりません。しかし正しい知識さえあれば、決して無暗に怖がる必要はないのです。
2005.05.15(日)
毎年冬から春にかけて、インフルエンザが猛威を振るいます。今年も例外ではなく、皆様の中にもインフルエンザで苦労された方が多数いらっしゃるのではないしょうか?インフルエンザには罹らなくても、この時期は「風邪」をひく人が、数にすればその数倍いるものと思われます。この季節は丁度受験シーズンなどとも重なるため、受験生の皆さんにとっては、「風邪」を予防することは「受験勉強すること」と同じくらい重要なことですね。
さて、動物病院にも、犬や猫が「風邪をひいたようだ」と言って連れて来る方が時折いらっしゃいます。我々も、症状がさほど著しくないような場合には、「風邪のようなものかもしれませんね」と言うような言い方をして様子を見ることもあります。犬や猫などの動物は本当に「風邪」をひくのでしょうか?
動物に「風邪」という病気があるかどうかを考えるためには、その前に「人の風邪」について、正確に知っておく必要があります。私達は日常的に「風邪」という言葉を使っていますが、では一体「風邪」とは何なのか、ここで確認してみましょう。
「風邪」と言うのはひとつの疾患を言い表す「病名」ではありません。2003年に「日本呼吸器学会」がまとめた診療指針「成人気道感染症診療の基本的考え方」によると、いわゆる「風邪」とは、急性の上部気道炎(喉から鼻までの炎症)で主にウイルス感染が原因であり、発熱、鼻汁、喉の痛みや咳などの症状がみられるものの総称ということになっています。そして、インフルエンザやその他の細菌感染などと区別するように、以下のようなポイントが挙げられています(以下抜粋)。
1)普通は3-4日(中には14日程度かかるものもある)で自然に治る。風邪薬で治るものではない。
2)ウイルス感染なので抗生物質は効かない。
3)発熱は身体がウイルスと戦っている証拠であり、ウイルスの増殖を抑えるのに必要な免疫反応である。
4)したがって、解熱・鎮痛剤は症状が余程ひどくない限りむやみに使用しないほうが良い。
5)手洗い、うがいで予防することが大切
つまり、「風邪」とはウイルスによる上部気道感染で、栄養と休養をしっかり取れば通常1週間前後で治ってしまうので原則的に病院で治療したり薬を飲んだりする必要はなく、予防が大切、ということになります。ちなみに、インフルエンザは咳やくしゃみなどからの飛沫感染が主な感染経路ですが、通常の「風邪」の場合にはウイルスに汚染された指で目や鼻の粘膜などを触ることによって感染する「接触感染」がメインの感染経路であることが知られているそうです。つまり「風邪」の予防にはうがいよりもむしろ、手洗いのほうが重要性が高いということになります。
それでは、動物にはここで挙げた条件に合致するような「風邪」に当たる病気は存在するのでしょうか?
猫には俗称「猫カゼ」と呼ばれるウイルス疾患があることが知られています。この病気は正確には「猫伝染性鼻気管炎(FVR)」と言って、ヘルペスウイルスの一種が原因で起こる猫の伝染病です。この病気は特に子猫で重症の鼻炎や上部気道炎を引き起こし、同時に角膜炎や結膜炎など「目の粘膜」にも激しい炎症を引き起こします。中には固まった鼻汁と目ヤニで目が開かなくなってしまったり、結膜が癒着してしまうようなケースもあります。体力の無い子猫では、症状が重度な場合には衰弱して命を落としてしまうこともあります。またヘルペスウイルスの特徴として、症状が改善して一見治ったように見えても、慢性化して後で再発したり、慢性鼻炎として症状が一生涯継続することも稀ではありません。したがって、この病気は「治療しなくても数日で治ってしまう」風邪とは「かなり違う病気」であることが解ります。つまり「猫カゼ」は明らかに「風邪」ではありません。
では犬ではどうでしょうか?犬には通称「ケンネルコフ*」と呼ばれる伝染性の呼吸器病があります。ケンネルコフは別名「伝染性気管気管支炎(ITB)」などと呼ばれることもありますが、人の風邪の場合と似ているのは、この病名が「幾つかの病原体を原因とする呼吸器疾患」の総称であるという点です。では「ケンネルコフ」は「風邪」なのでしょうか?ケンネルコフは、その別名であるITBという呼び名からも解るように、「気管支炎」を効率に引き起こします。気管支炎は、もう少し症状が進行すればすぐに「肺炎」へと移行します。肺炎は「上部気道炎」ではありません。もちろん人の風邪の場合でも、こじらせて肺炎になる場合が無いとは言えませんが、かなり稀なケースではないでしょうか?ケンネルコフの原因となる病原体の中には確かに、比較的症状が軽く、殆ど治療らしい治療を必要とせずに数日で改善してしまうものも含まれてはいます。しかし、中には非常に重症化し、数週間から数ヶ月の治療を要するものも珍しくありません。そして初期段階ではこれらを区別することが非常に困難なのです。ですから人の風邪と同じように軽く考えてしまうと治療のタイミングを逃してしまい、危険な場合もあります。
という訳で、私の結論としては「猫には風邪はない」「犬には風邪と似たような病気があるのかも知れないが、初期に正確な診断を下せないため『風邪』だとは思わないほうが良い」と言うことになるのですが、皆さんのお考えは如何でしょうか?
*ケンネルコフ:”kennel cough”;本来の発音からすると「ケネルコフ」と表記するのが正しいと思われますが、ケンネルコフが一般的な様なのでここでも「ケンネル・・・」を使用しました。
2005.04.12(火)
最近気になるフレーズのひとつが「自然治癒力を高める」である。これは様々な健康食品やサプリメント類、民間療法などの効果をアピールする際のキャッチコピーとして、非常に一般的に使用されている。デパートの健康食品売り場に行っても、ドラッグストアのサプリメント売り場に行っても、「自然治癒力を高める」もので溢れ返っている。自然治癒力が高まると、なんだか病気にならないような気がするし、怪我をしてもすぐに治るような気がして、とても有難いことのように感じてしまうのが人情かもしれない。
本来、医薬品ではないものについて、効能・効果をうたってはいけない(薬事法違反になるので)のだが、「自然治癒力を高める」とか、「免疫力を高める」ということは、それ自体が非常に定義が曖昧で、どのような意味にも捕らえることが可能で、しかも実は「何も意味していない」という可能性もあるため、非常に便利に使われているのだろう。
しかし、特に最近色々な「傷の治療」をしている中で感じるのだが、「自然治癒力」は本当に「高める」ことができるのだろうか?傷の治療に関してときどき受ける質問の中に、「傷の治癒を早める薬などはありませんか?」というのがある。確かに「傷の治癒を早める効果がある」として売り出されてる(動物用)医薬品、医療材などがない訳ではない。しかしこれらの殆どに対して、私自身は懐疑的である。
「創傷治療」のところでも紹介されているが、私が現在行っている傷に対する治療;消毒をせず、乾燥を防いで、ドレッシング材などを利用しながらの治療では、今までの治療よりも非常に早く傷が治ることが多い。しかし私自身は、「傷の治癒を早めている」とは考えていない。これは、傷の治癒を邪魔している様々な「阻害因子」を取り除くことで、本来生体が持っている治癒のスピードに『戻している』だけだと考えている。つまり、「マイナス」のスピードから「ゼロ」に近づけているだけなのである。従って、組織が持っている本来の治癒のスピードである「ゼロ」のレベルにまで達してしまったら、それ以上スピードを「プラス」の方向に上げることは多分できないと思うのである。もしも組織の細胞が本来持っている能力よりも『早く』増殖、分裂するならば、それはまるで「癌」のような状態ではないだろうか??
だから、「傷の治癒を早める」と謳っている医療材・薬剤の多くは、それに含まれている基材のお陰で傷の乾燥を防いでいたり、消毒する機会が減ったり、ガーゼが傷にくっ付かなくなったりするなど、意図しない副次的な効果により「たまたま」傷が早く治っただけなのではないだろうか?と考えるのである。しかもこれらの効果を実証するために比較されている治療法は、「消毒してガーゼを当てる」方法なのであるから、どんな方法でもこれより早く治るのは当然のことである。多分、中に含まれている薬剤の効果などは、殆ど関係がない。
そもそも傷が治らないのは「原因を除去」しないからであって、全ての傷は自ら治癒する能力を持っている。だから我々ができることは、「原因となっている因子」を除去しつつ、治癒の邪魔をしないこと(本来の治癒しやすい環境を整えること)であって、「特効薬」を塗ることではない。だいたい原因も何も関係なく「付けただけで何でも治る特効薬」など存在しないのである。
そういう訳で、「傷」に限らず生体にとって「正常な状態」以上に「治癒力を高める」などということは、本来ありえないはず、と考えるのである。病気で体力が落ちている場合や、栄養不良などで免疫が低下している場合には、病原体を除去したり、栄養状態を改善させることで「自然治癒力(免疫力)」を正常に近い状態にまで引き上げることはできるだろう。『マイナス』から『ゼロ』に引き上げることは可能なのだ。つまり、それが「医療行為」とも言えるのだろう。しかし『ゼロ』の状態からさらに『プラス』に引き上げることは恐らく出来ないのである。健康な状態はそれを維持するのが正常な「恒常性」なのであって、それよりもさらにどんどん「健康になる」ことは出来ないのである。「正常値」は、それより低くても、高くても「異常」だ、というのと同じことかもしれない。
「普通」が一番「健康的」なのである・・・・。